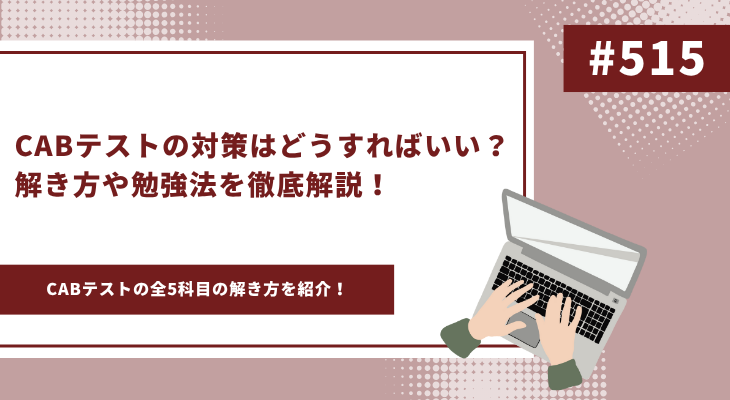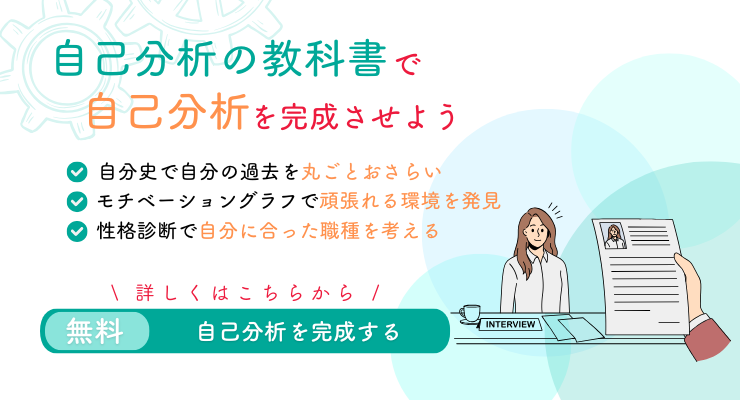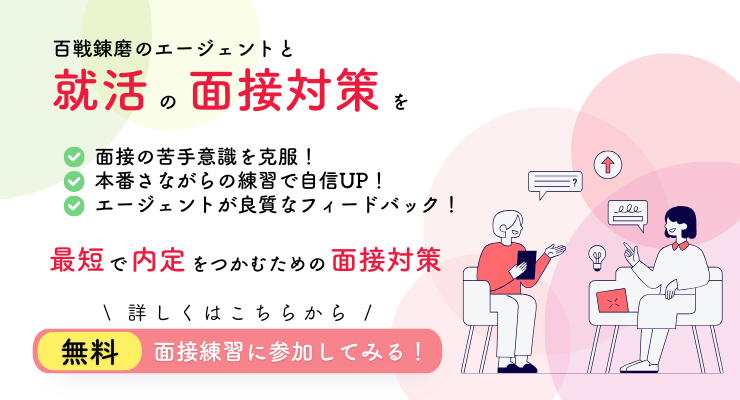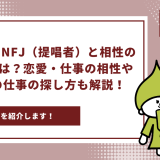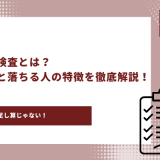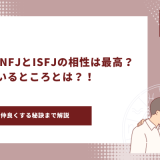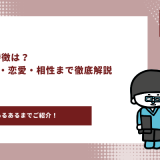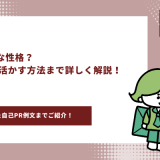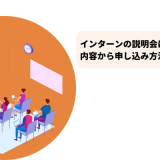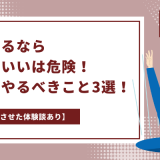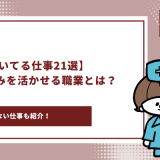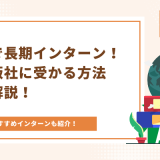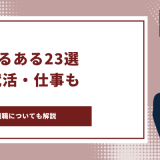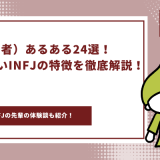IT企業の選考で課されることが多いCABテストについて、不安を感じている方は多いと思います。
実際、SPIとは違う独特な問題形式に、「どう対策すればいいの?」と戸惑う就活生は少なくありません。
この記事では、CABテストの基本から、科目別の具体的な対策方法、高得点を狙うための勉強のコツまで、網羅的に解説します。
最後まで読めば、CABテストへの苦手意識がなくなり、自信を持って本番に臨むことができるでしょう!
こんな人に読んでほしい
- CABテストがどのようなものか知りたい人
- CABテストの解き方が知りたい人
- CABテストの勉強法が知りたい人
CABテストとは?
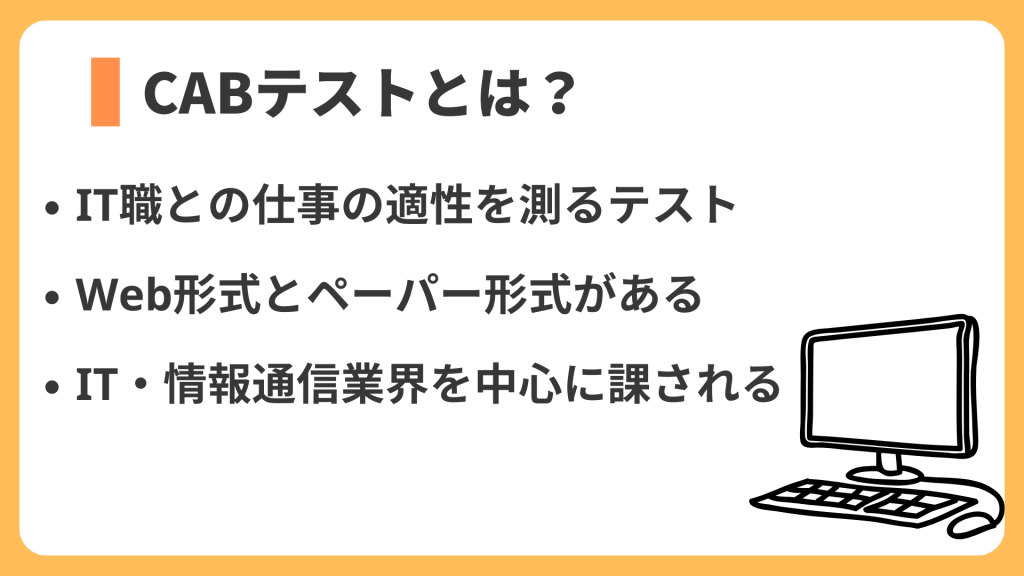
CABテストとは、主にIT系の職種で求められる論理的思考力や情報処理能力といった、仕事への適性を測るためのテストです。
企業は、システムエンジニアやプログラマーなどに必要な資質(複雑なシステムの理解力など)を持つ人材を効率的に見極めるためにCABテストを導入しています。これによって、企業は入社後のミスマッチを防ごうとしています。
CABテストは、単なる学力ではなく、コンピュータ職に不可欠な思考のプロセスや性格的な適性を評価するテストとして、多くのIT企業やコンサルティング業界で活用されています。
CABテストの形式
CABテストには、自宅などで受けるWeb形式(Web-CAB)と、テストセンターなどの会場で受けるペーパー形式の2種類があります。この2つは問題数や制限時間、一部の科目が異なります。
Web-CABの方が制限時間も短く、一般的に難易度が高いと言われています。例えば、計算問題ではWeb-CABが「四則逆算」、ペーパー形式が「暗算」といった違いがあるので、自分が受ける形式の特徴を事前に理解しておくことが大切です。
SPIやGABとの違い
CABテストはIT職への適性に特化しているのに対し、SPIは総合的な能力、GABは総合職向けの能力を測ることを目的としています。
このように、企業が求める職務や役割に応じて、最適な人材を見極めるために異なるテストを使い分けています。
また、CABテストは図形を用いた問題が多くプログラミングの素養を測るのに対し、SPIやGABは言語能力なども含めて総合的に評価する、という違いがあります。
CABテストを導入している企業
CABテストは、IT・情報通信業界を中心に、コンサルティング業界や金融機関のIT部門などで導入されています。
これらの業界・職種では、システムの設計やデータ分析など、論理的思考力が業務の成果に直結します。そのため、CABテストを課すことで、そうした業務に適性があるかどうか見分けています。
過去には以下のような企業でCABテストが導入されました。
- 富士通
- カプコン(プログラマー職)
- 日立ソリューションズ・クリエイト
- NTTコミュニケーションズ
- Amazon
ただし、採用年度によってテスト形式は変更される可能性があるので、必ず志望企業の最新情報を確認しましょう。
CABテストの解き方
CABテストは以下の5科目で構成されていて、科目ごとに特徴と対策法が異なります。
- 暗算(四則逆算)
- 法則性
- 命令表
- 暗号
- 性格検査
それぞれの科目が、論理的思考力や情報処理能力を測定するために作られているため、各科目の出題傾向を理解し、それに合った対策をすることが高得点への鍵となります。
① 暗算(四則逆算)
暗算(四則逆算)は、速さと正確性が求められる科目です。この科目は、概算で選択肢を絞ることがとても大切です。
Web-CABでは1問あたり約10秒で解く必要があり、全ての計算を正確に行っていたら最後まで解くのは難しいです。
例えば「49×502」のような問題なら、「50×500=25000」と大まかに計算し、最も近い選択肢を選びます。日頃から計算練習を繰り返し、スピードを上げておくことが重要です。
② 法則性
法則性の問題は、図形変化の典型的なパターンを事前に暗記しておくことで、解答時間を大幅に短縮できます。
出題される法則には「回転」「反転」「色の変化」「数の増減」など、ある程度の決まったパターンがあるため、これらを知っているだけで素早く法則を見抜けるようになります。
問題集を繰り返し解き、これらの頻出パターンに慣れることで速く正確に法則性の問題を解くことができるでしょう。
③ 命令表
命令表は、与えられた命令を一つずつ正確に図形に適用していく問題です。命令表の問題は、焦らずに手を動かして図の変化を追っていくことが重要です。
複数の命令が重なると頭の中だけで処理するのは難しく、ミスをしやすくなるので、練習の段階から、問題用紙の余白に図形の変化を書き込みながら解く癖をつけると、本番でも落ち着いて対応することができるでしょう。
④ 暗号
暗号問題は、変化前と変化後の図形を比較し、どの暗号がどのような変化に対応するのかを解読する問題です。これは、法則性と命令表の応用問題と捉えておきましょう。
この問題では、図形変化の法則を見抜く力(法則性)と、その法則を他の図形に適用する力(命令表)の両方が同時に試されます。複数の例を見比べて共通のルールを探し、メモを取りながら整理するのが攻略のコツです。
⑤ 性格検査
性格検査では、正直かつ一貫性のある回答を心がけることが最も重要です。
企業は回答内容から学生の人柄や価値観を把握し、自社の文化に合うかを見ています。
嘘の回答や矛盾した回答は信頼性を損なう可能性があるので注意しましょう。
性格検査の対策として、事前に自己分析を深め、自分の強みや価値観を明らかにしておくことが効果的です。
自己分析をするときにおすすめなのが、「自己分析の教科書」です。
自己分析の教科書は、手順に沿って自己分析を進めていくだけで、自分の強みや弱み、価値観や将来のビジョンまでわかります。
無料で簡単に自己分析ができるので、ぜひ利用してみてくださいね!
CABテストの勉強法
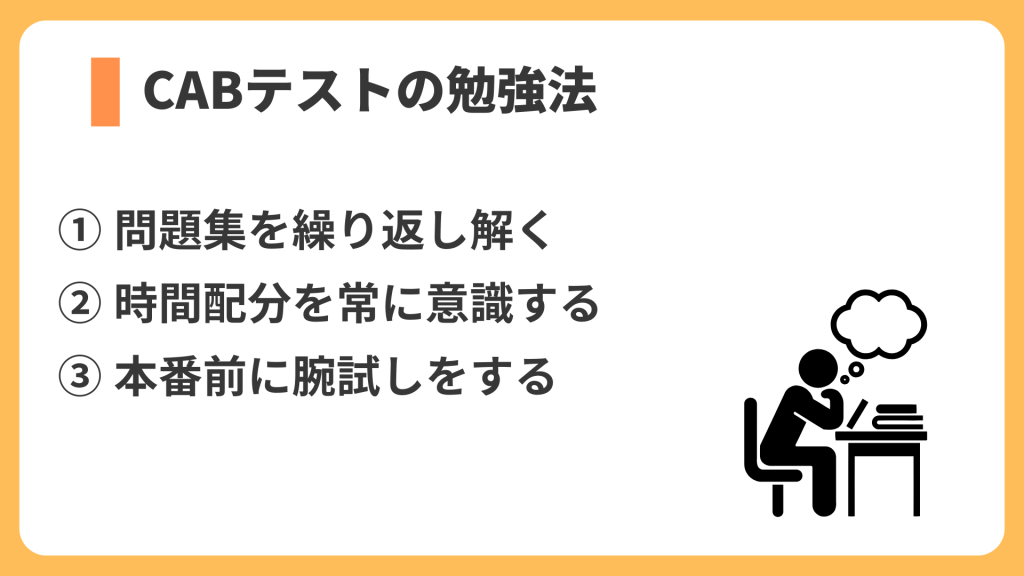
CABテストの攻略には「問題集の反復」「時間配分の徹底」「苦手分野の克服」という3つのステップが不可欠です。
CABテストで高得点を狙うときは、知識量を増やすことよりも、問題に慣れることが大切です。CABテストの独特な問題形式に慣れ、時間内に解き切るスピードを身につけるようにしましょう。
① 問題集を繰り返し解く
CABテストの対策をするときは、多くの参考書に手を出すのではなく、まずは1冊の問題集を完璧になるまで繰り返し解くこようにしましょう。
問題はパターン化されているため、同じ問題を繰り返し解くことで解法パターンが自然と身につき、解答スピードが向上します。
1周目は問題形式に慣れる、2周目は時間内に解く、3周目は苦手分野をなくす、といったように目的を持って取り組むと良いでしょう。
② 時間配分を常に意識する
CABテスト対策で最も重要なのは時間配分です。そのため、時間配分を常に意識しながら勉強することが大切です。
CABテストは問題数に対して制限時間が非常に短く、満点を狙うのは非現実的であり、合格ラインである6割程度の正答率を目指し、時間切れで解ける問題を落とさないようにしましょう。
CABテストの勉強をするときは、「1問30秒まで」など自分なりのルールを決め、分からない問題は勇気を持って飛ばす意識を常に持つようにしましょう。
③ 本番前に腕試しをする
第一志望の企業の選考を受ける前に、CABテストを導入している他の企業で本番のテストを経験しておくことが大切です。
問題集での練習と本番の緊張感は全く異なります。事前に本番の雰囲気に慣れておくことで、実力を最大限に発揮できるようになります。
また、複数回受験すると「見たことがある問題」に出会う確率が高まることもあります。志望度が高くない企業であっても、貴重な練習の機会と捉えて受験してみると良いでしょう。
CABテスト対策と並行してすべきこと
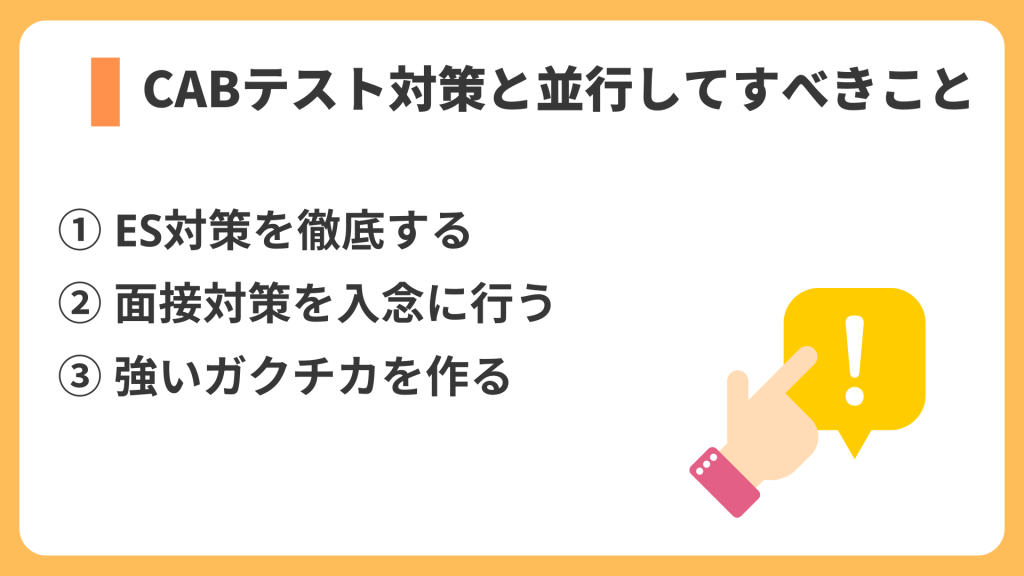
CABテストの対策はとても重要ですが、それだけで就活は終わりません。CABテストを通過した後の選考を見据えて、他の準備も同時並行で進めることが、志望企業から内定をもらうために必要です。
ES対策を徹底する
CABテストを突破すると、次に待っているのがES(エントリーシート)選考です。せっかくCABテストを通過できても、ESの準備が疎かだと、面接まで進めない可能性があります。
そのため、自己PRやガクチカをESでしっかりとアピールすることが大切です。
しかし、ESの書き方がよくわからず困っている就活生の方も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめなのが、「SmartES」です。
SmartESは、選考を突破した10万本のESを学習した生成AIが短時間でESを作成することができるツールです。
SPI対策に時間がかかってしまってESを書く時間が無い人や、ESで落ちてしまって困っている方は、ぜひ利用してみてくださいね!
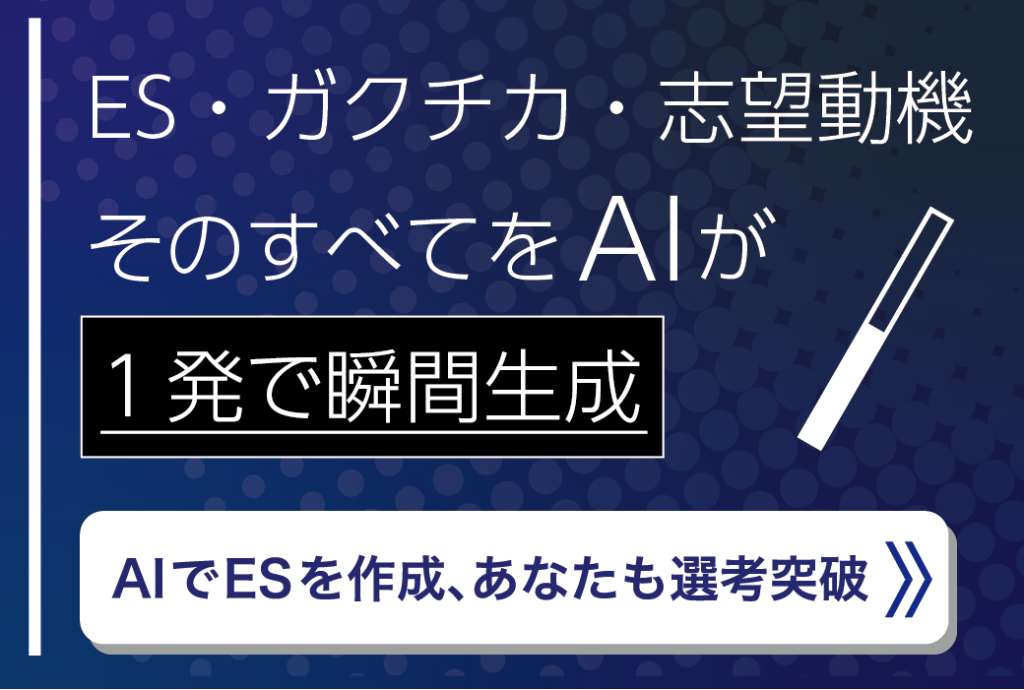
ESやガクチカで困っているならES生成AIであるSmartESがおすすめです!
ES生成AIとは就活や長期インターンのサポートに特化した生成AIのことです。
ES生成AIであるSmartESに質問とそれに対する簡単な回答を打ち込むと、自動でES、ガクチカ、志望動機を生成してくれます!
SmartESの強みは以下の4つです!
- 数々の選考を勝ち抜いてきた10万本以上の良質なESをもとに生成しているため、就活に最適化されたESを出力できる!
- 入力するべきことがフォーマット化されていて簡単なので、複雑な指示は必要ない!
- 企業のURLを入力するだけで、その企業に合った志望動機を出力することが可能!
- 自分一人ではやりづらい添削もAIがやってくれる!
「ESやガクチカでどんな文章を作ればいいかわからない……」「作れたけどちゃんと良いものになってるか不安……」という人はES生成AIを使ってみてはいかがでしょうか?
SmartESを利用するにはこちらをクリック
面接対策を入念に行う
就活ではCABテストの対策だけではなく、面接の対策もすることが大切です。
面接の対策をするときにおすすめなのが、「就活面談」です。
就活面談は、就活のプロが学生さんに寄り添いながら、就活対策を進めることができるサービスです。
就活のプロに面接のときのコツを聞くことができたり、面接の練習などを一緒にすることができます。また、企業からの視点も踏まえたアドバイスをもらうことができるので本当におすすめです。
無料でオンラインで行うことができるので、面接に自信のない学生の方はぜひ面談を受けてみてくださいね。
強いガクチカを作る
就活では、ガクチカ(学生時代に頑張ったこと)を重要視する企業が多く、面接やESでほぼ必ず聞かれます。
そのため、志望企業から内定をもらうためには、強いガクチカを作ることが大切です。
強いガクチカを作るときにおすすめなのが、長期インターンです。
長期インターンは、目標に向かって頑張った経験として面接やESでアピールしやすいのが特徴です。また、長期インターンに参加することで、他の就活生との差別化を図ることができるため、就活で有利になることができます。
ココシロインターンでは学生さんに寄り添って、どういった目的で働くのか、条件決めまでなども一緒に行い、長期インターン探しのサポートをします。
また、どのような業務が向いているか、どのような雰囲気の企業が合いそうか、企業選定まで行います。
一人一人に合わせて、しっかりと対策をしてくれるので安心して長期インターンを始めることができます!
このようなサービスを最後まで無料で受けることができるのは、ココシロインターンだけです!
ぜひ一度、オンライン面談を受けてみてくださいね!
学生の面談申し込みはこちら
まとめ
本記事では、以下の内容をお伝えしました。
- CABテストはIT職への適性を測るテストである
- CABテストは暗算や法則性などの5科目で構成されている
- CABテスト対策は問題集の反復をすることと、時間配分の意識をもつことが大切である
- CABテストの対策以外にもESや面接の対策をすることが大切である
CABテストはIT職への適性を測るためのものであるため、IT業界に興味がある人は入念に対策をするようにしましょう。
CABテストは暗算や法則性などの5科目で構成されており、それぞれの科目の解き方を理解しておくことが大切です。
また、CABテストの対策をするときは、一冊の問題集を繰り返し解くことと、時間配分の意識を常に持つことが効果的です!
人気記事