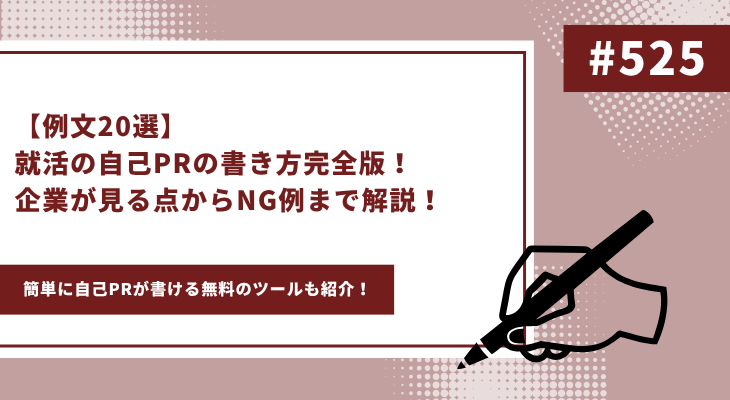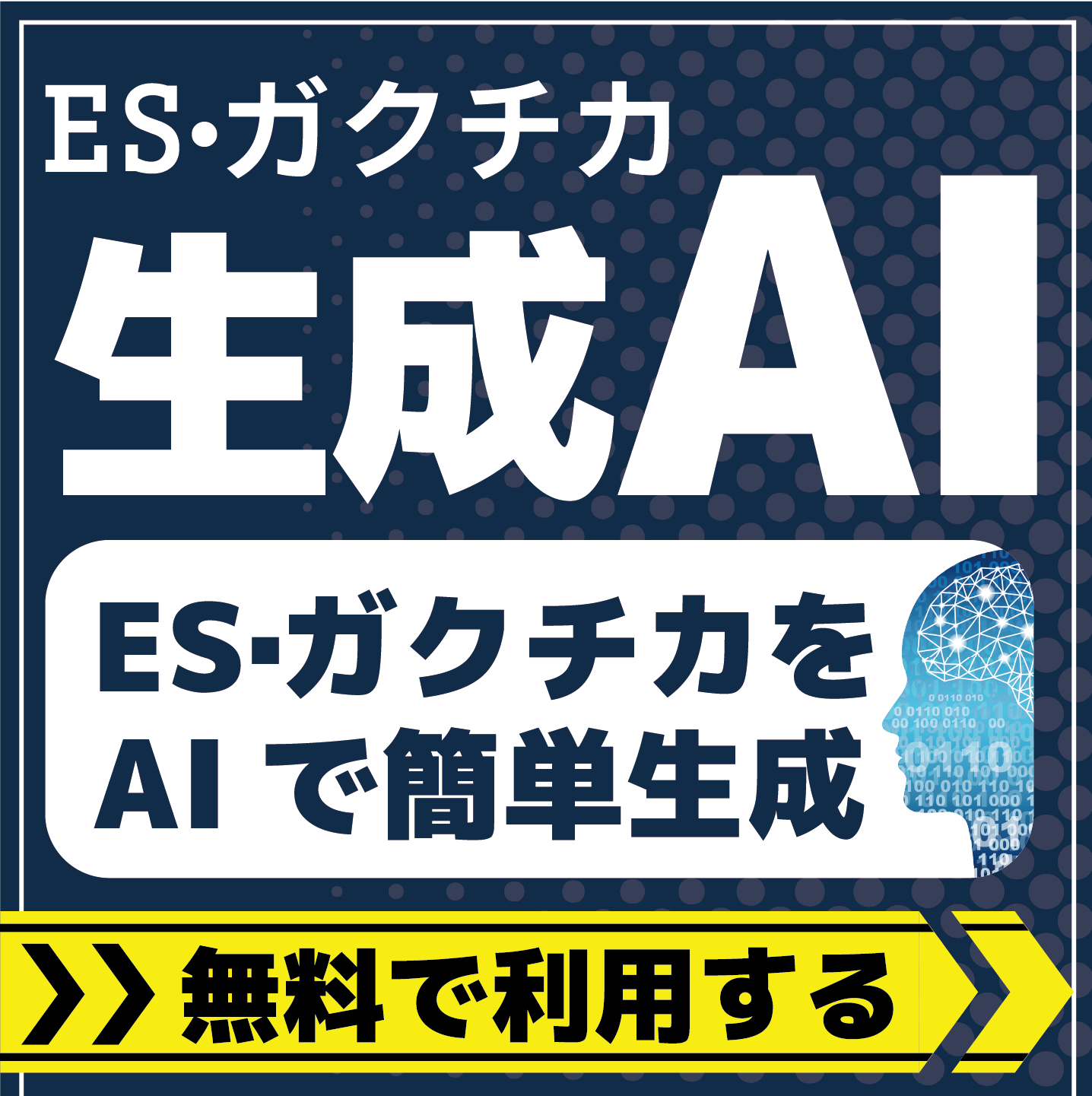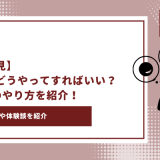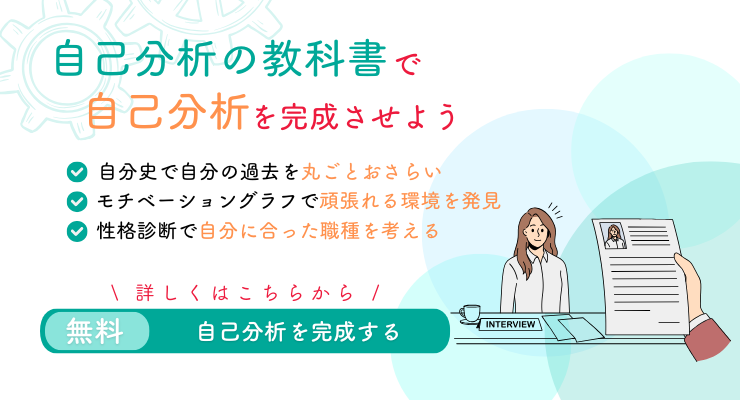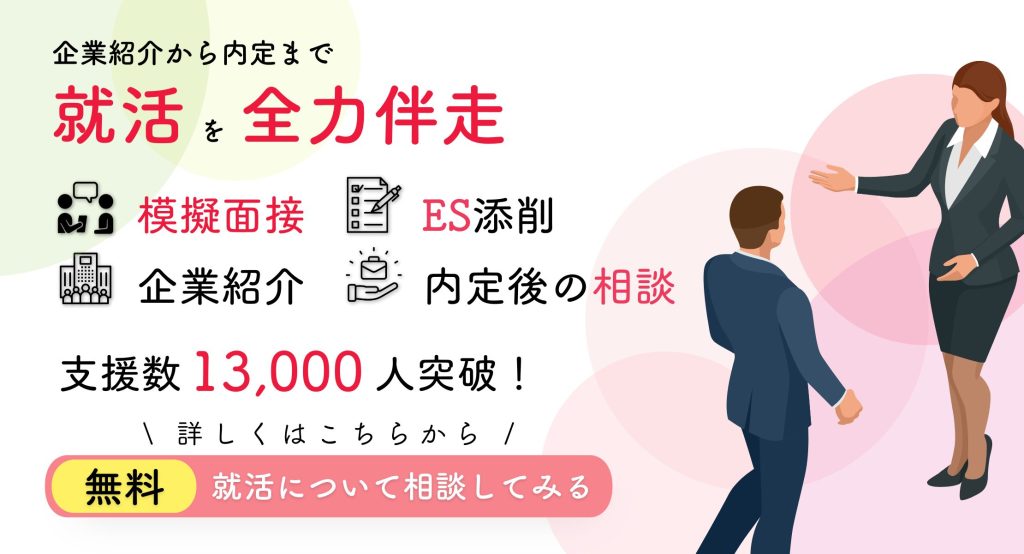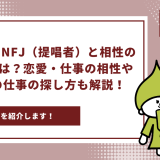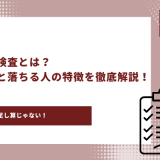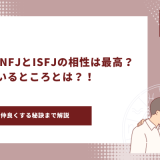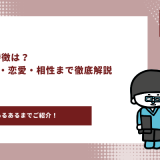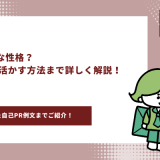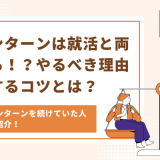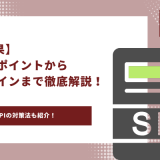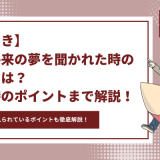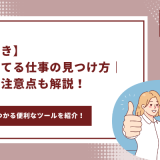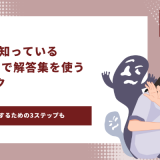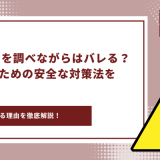就職活動で必ずと言っていいほど求められるのが、自己PRです。
しかし、いざ書こうとしても、「何を書けばいいの?」「自分の強みって何だろう?」と手が止まってしまう就活生も多いのではないでしょうか?
自己PRは、正しい書き方とポイントさえ押さえれば、誰でも採用担当者の心に響くものを作成できます。
この記事では、自己PRの基本的な考え方から、企業が何を見ているのか、そして具体的な書き方まで、詳しく解説していきます!
こんな人に読んでほしい
- 自己PRの書き方がわからず、困っている人
- 企業は自己PRのどこを見ているのか知りたい人
- 自己PRの例文が見たい人
就活の自己PRとは?
そもそも、就活における自己PRって何なのでしょうか?
就活における自己PRとは、「自分の強みやスキルを入社後にどう活かせるか」を企業にアピールすることをいいます。
企業は自己PRを通じて、学生が自社の利益に貢献してくれる「ポテンシャル」を持った人材なのか判断したいと考えています。
つまり、自己PRはあなた自身を企業に売り込むための「プレゼンテーション」なんです。
そのため、混同しがちな「自己紹介」や「長所」とは目的が異なります。
自己紹介は「自分を知ってもらうこと」、長所は「自分の良い点を伝えること」が目的ですが、自己PRは「自分の強みで会社に貢献できることを証明すること」がゴールです。
就活の自己PRを通して企業が見ているもの
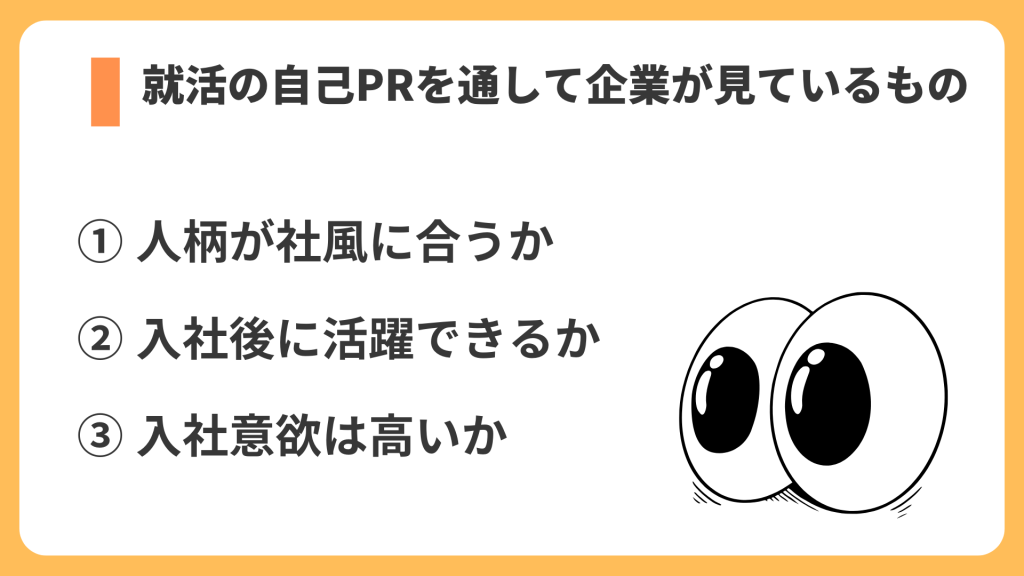
採用担当者は毎日何十、何百というESを読んでいます。
そのため、採用担当者があなたの自己PRから何を知りたいのか、その「視点」を理解することが、自己PRを作成するにあたって、とても大切です。
企業にとって採用活動は「投資」です。
だからこそ、長く活躍してくれて、自社の文化に合い、高い成果を出してくれそうな人材かを慎重に見極めたいんです。
①人柄が社風に合うか
企業は、あなたの強みや物事への取り組み方が、企業の文化や価値観と合っているかを見ています。
どんなに優秀な学生でも、社風に合わなければ早期離職のリスクが高まってしまいます。
例えば、「挑戦」を重んじるベンチャー企業に「安定性」や「慎重さ」をアピールしても、響きにくいかもしれません。
企業のHPや社員インタビューを読み込んで、どんな人柄が求められているかを把握するようにしましょう。
②入社後に活躍できるか
企業はあなたの強みや経験が、入社後の具体的な業務で再現性をもって発揮されるかを見ています。
企業は即戦力だけでなく、将来の成長可能性、つまり「ポテンシャル」を重視しています。
そのため、自己PRを通して、あなたのポテンシャルを企業に納得させる必要があります。
「私の強みはリーダーシップです」と伝えるだけでは不十分です。
「リーダーシップを発揮して文化祭の企画を成功させ、昨年度比150%の来場者数を達成しました。この経験で培った周囲を巻き込む力は、貴社のプロジェクトマネジメント業務でも必ず活かせます」のように、過去の実績と未来の貢献を繋げて話すことが重要です。
③入社意欲は高いか
企業は、自己PRの内容の深さや具体性から、どれだけ真剣に自社を志望しているかを見ています。
内定辞退による企業の損失は大きいため、本当に自社に入社してくれる、志望度の高い学生を採用したいと考えているからです。
誰にでも言えるような薄い内容の自己PRは、「志望度が低い」と判断されかねません。
自己PRで企業の事業内容や理念に触れ、「だからこそ、自分のこの強みが活かせると思った」と語ることで、説得力と入社意欲を同時に示せます。
「なぜこの会社でなければならないのか」という問いに、あなた自身の言葉で答えられるように準備しましょう。
就活の自己PRを書けるようになるには?
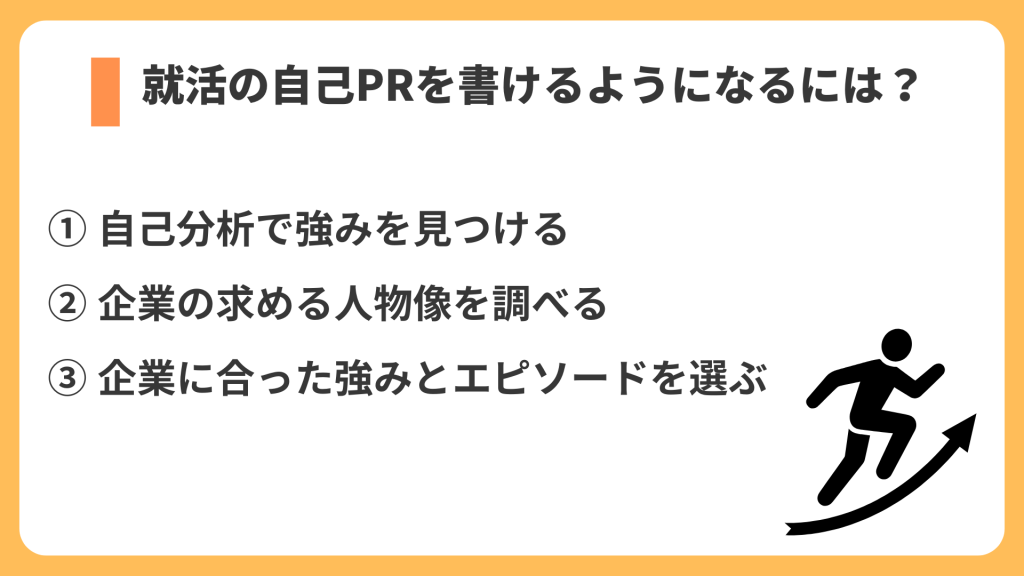
やみくもに書き始めても、良い自己PRは作れません。
ここでは、自己PRを書けるようになるためのステップを解説していきます。
Step1: 自己分析で強みを見つける
まず、過去の経験(成功体験、苦労したこと、人から褒められたこと)を洗い出し、共通する自分の行動や価値観から強みを発見しましょう。
自分のことは、意外と自分では分かっていないものです。客観的に過去を振り返ることで、自分では当たり前だと思っていた行動の中に、アピールできる「強み」が隠されていることに気づけます。
具体的な方法としては、以下のようなものがあります。
- 自分史
- モチベーショングラフ
- 他己分析
- マインドマップ
自己分析の方法は、自分史を書くことや、モチベーショングラフを作成することなど、たくさんの方法があります。
詳しい自己分析の方法は、下記記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてくださいね!
自己分析をするときに、おすすめなのが自己分析の教科書です。
自己分析の教科書では、手順に沿って項目を埋めていくだけで、自己分析を完結させることができます。
無料で手軽に自己分析を進めることができるので、ぜひ利用してみてくださいね!
Step2: 企業の求める人物像を調べる
次に、企業の採用サイト、IR情報、社員インタビューなどを読み、その企業がどんな能力や価値観を持つ人材を求めているかを調べるようにしましょう。
企業ごとに求める人物像は異なります。自分の強みを一方的にアピールするのではなく、相手が「欲しい」と思っている強みを提示することが、とても大切です。
また、中期経営計画などから会社の未来の方向性を知ることでも、求められるスキルがわかるかもしれません。
Step3: 企業に合った強みとエピソードを選ぶ
最後に、自己分析で見つけた自分の強みと、企業の求める人物像の、両方に合致する具体的なエピソードを選びます。
この「重なり」こそが、自己PRで最もアピールすべきポイントなのです!
この重なりを伝えることで、企業は「この学生はウチにぴったりだ」と納得してくれます。
例えば、「自分の強み:粘り強さ」と「企業の求める人物像:困難な課題にも最後まで取り組む人材」が重なれば、「大学の研究で、誰も成功しなかった実験に半年間粘り強く取り組んだ経験」を選ぶと良いでしょう。
これが説得力のある自己PRの核心となります。
【テンプレート付き】就活で差がつく自己PRの書き方
自己PRの材料が揃ったら、いよいよ文章を作成していきます。
自己PRは構成とコツをおさえることが大切です。
ここでは、自己PRの基本的な構成と、コツを解説していきます。
自己PRの構成
自己PRの構成は、下記のようにすると良いといわれています。
自己PRの構成
①:強みを一文で言い切る(結論)
②:エピソードで裏付ける(具体例)
③:入社後の貢献を伝える(貢献)
強みを1文で言い切る
まず冒頭で「私の強みは〇〇です」と、最も伝えたい自分のアピールポイントを簡潔に述べます。
結論から話すことで、採用担当者は話の全体像を掴みやすくなり、その後の話に集中できます。ここが曖昧だと、最後まで何が言いたいのか伝わらないリスクがあります。
エピソードで裏付ける
次に、強みの根拠となるエピソードを、「状況→課題→行動→結果」の順で具体的に説明します。
エピソードの具体性が、あなたの強みの説得力を決めます。客観的な事実や数字を盛り込むことで、あなたの話にリアリティと信頼性が生まれます。
入社後の貢献を伝える
最後に、その強みを活かして、入社後にどのように企業に貢献したいかを述べましょう。
企業が最も知りたいのは「未来」の話です。あなたを採用することで企業にどんなメリットがあるのかを具体的に示すことで、採用担当者はあなたと一緒に働く姿をイメージしやすくなります。
自己PRのコツ
自己PRを書くときのコツには、以下のようなものがあります。
自己PRのコツ
①:具体的な数字や固有名詞を使う
②:キャッチフレーズで強みを言い換える
③:強みとエピソードに一貫性を持たせる
具体的な数字や固有名詞を使う
完成した文章をさらに良くするために、「頑張った」「多くの」といった曖昧な表現を避け、数字や固有名詞を使って具体的に表現しましょう。
数字は客観的な事実であり、誰が読んでも同じように成果の大きさを理解できます。これにより、あなたの話の信憑性が格段に高まります。
例:「売上を上げるために頑張りました」→「〇〇という新商品を提案し、前月比120%の売上向上に貢献しました」
キャッチフレーズで強みを言い換える
「コミュニケーション能力」のようなありきたりな言葉を、自分らしい言葉で表現してみましょう。
採用担当者は、同じような強みを何百回も見ています。キャッチーな言葉を使うことで、その他大勢の中に埋もれるのを防ぎ、強い印象を残すことができます。
例:「継続力があります」→「私は『毎日1%の改善を続ける』ことを信条とする人間です」のように、あなたの人柄が伝わるオリジナルの表現を探してみましょう。
強みとエピソードに一貫性を持たせる
最後に、冒頭で述べた強みと、それを裏付けるエピソードの内容が、論理的にしっかりと結びついているかを確認します。
強みとエピソードにズレがあると、「本当にその強みがあるの?」「論理的思考力が低いのでは?」と疑われてしまい、説得力がなくなります。
「私の強みは計画性です」と述べたのに、エピソードが「突発的なトラブルに対応した」という内容では、アピールしたい強みがブレてしまいます。
この場合は、強みを「柔軟な対応力」に変更するか、計画性を発揮した別のエピソードを探す必要があります。
自己PRが簡単に作れる便利なツール
「自己PRの構成は分かったけど、実際に書くのは大変…」だと考えている人におすすめなのが、「SmartES」です。
SmartESを使えば、1万件以上の選考を突破したESを学習したAIにESを作成させることができます。
ESを書くことが苦手な人や自己PRを書くことが大変だと感じる人は、ぜひSmartESを利用してみてくださいね!
SmartESを利用するにはこちらをクリック
就活生の自己PR体験談
実際に就活を乗り越えた先輩たちも、最初は自己PRに悩んでいました。
ここでは、先輩たちが自己PRの悩みをどのように解消したのか、体験談を紹介していきます。
体験談①:すごい経験がなくて悩んだAさん

周りが留学や長期インターンの話をする中、私はコンビニのアルバイト経験しかなく、本当に焦っていました。
しかし、就活面談で相談したら『毎日続けていたことの中にこそ、あなたの強みがある』と言われたんです。
そこで、廃棄を減らすために発注方法を工夫続けた経験を『課題解決力』としてアピールしたところ、面接官から『地道な努力ができるんだね』と高く評価され、無事、第一志望の食品メーカーから内定をもらえました。
Eさんは、留学などのすごい経験はありませんでしたが、アルバイトでの経験を自己PRでアピールしたことで、見事、志望企業から内定をもらうことができました!
就活面談では、プロの就活アドバイザーが寄り添いながら、就活全般の対策を進めていくことができます。
就活での悩みを抱えている人や、面接対策を進めていきたいと考えている人は、ぜひ面談を受けてみてくださいね!
体験談②:強みが多すぎて絞れなかったBさん

私は就活を始めた当初、「リーダーシップも、計画性も、コミュニケーション能力もアピールしたくて、自己PRがごちゃごちゃになっていました。
ESも全然通らず悩んでいた時、SmartESを使ってみることにしました。
AIに自分の経験をいくつか入れたら、志望企業(ITベンチャー)に合わせて『主体性』を軸にした自己PRを提案してくれました。それに沿って自己PRを書き直したら、驚くほどスッキリして、その後の選考はスムーズに進みました。」
Mさんは、SmartESを利用したことで、ごちゃごちゃしていた自己PRを大幅に改善させることができました!
SmartESは、自己PRを書くのが苦手な人や、自分のアピールしたいことがまとまっていない人にはとてもおすすめです。
ESを通過させて、志望企業から内定をもらいたいと考えている人は、ぜひ利用してみてくださいね。
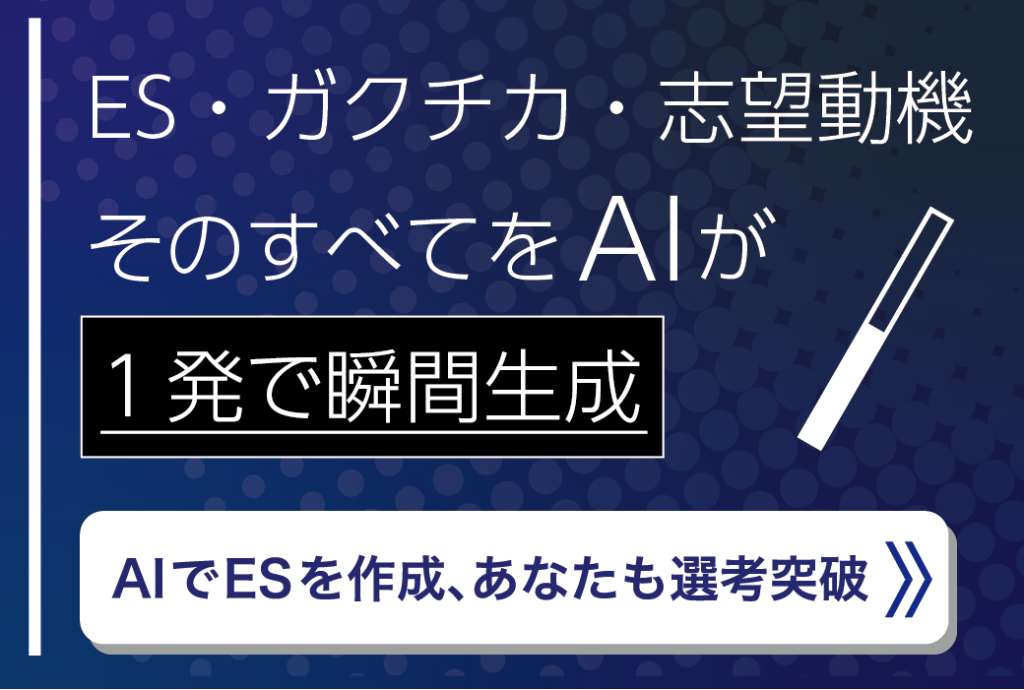
ESやガクチカで困っているならES生成AIであるSmartESがおすすめです!
ES生成AIとは就活や長期インターンのサポートに特化した生成AIのことです。
ES生成AIであるSmartESに質問とそれに対する簡単な回答を打ち込むと、自動でES、ガクチカ、志望動機を生成してくれます!
SmartESの強みは以下の4つです!
- 数々の選考を勝ち抜いてきた10万本以上の良質なESをもとに生成しているため、就活に最適化されたESを出力できる!
- 入力するべきことがフォーマット化されていて簡単なので、複雑な指示は必要ない!
- 企業のURLを入力するだけで、その企業に合った志望動機を出力することが可能!
- 自分一人ではやりづらい添削もAIがやってくれる!
「ESやガクチカでどんな文章を作ればいいかわからない……」「作れたけどちゃんと良いものになってるか不安……」という人はES生成AIを使ってみてはいかがでしょうか?
SmartESを利用するにはこちらをクリック
就活の自己PRのNG例
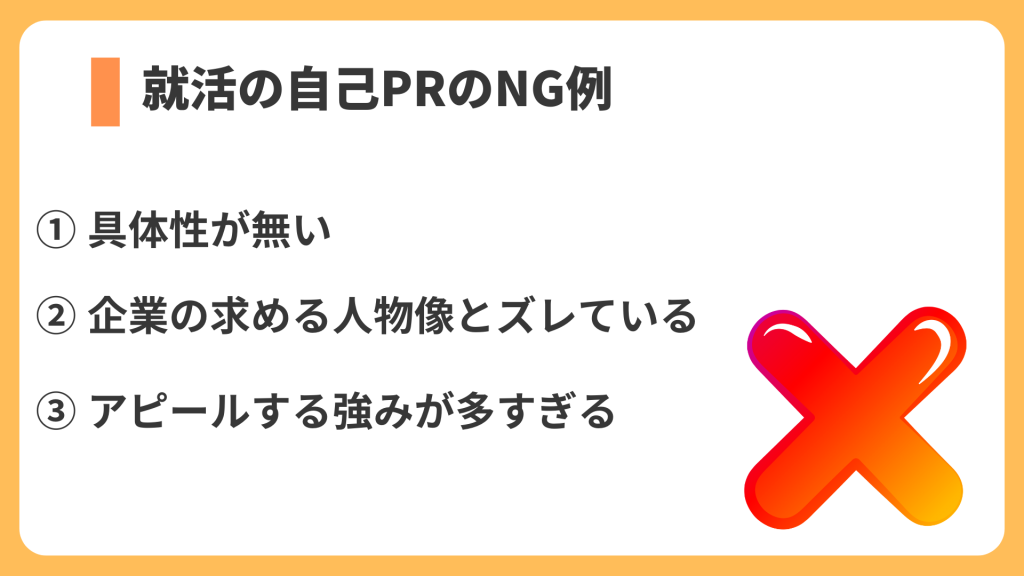
自己PRで、良かれと思って書いたことが、実はマイナス評価に繋がっているケースは少なくありません。
ここでは、多くの学生が陥りがちなNG例を紹介していきます。
NG例を知っておくだけで、あなたの自己PRの失敗確率をぐっと減らすことができるでしょう。
NG例①:具体性がない
「コミュニケーション能力を発揮し、頑張りました」のように、具体例が伴わない自己PRは評価されません。
これは誰にでも言えることであり、あなたの個性や能力が全く伝わらないからです。採用担当者は、あなたが「何をしたか」という事実を知りたいのです。
NG例②:企業の求める人物像とズレている
チームワークを重んじる企業に「個人で黙々と成果を出すのが得意です」とアピールするなど、企業の求める方向性と真逆の強みをアピールするのは避けましょう。
「この学生はうちの会社を理解していないな」「入社しても合わなそうだな」と思われてしまいます。自己PRは、あくまで企業とのマッチングを確認する場だということを忘れないでくださいね。
NG例③:アピールする強みが多すぎる
一つの自己PRの中に、複数の強みを詰め込むのもNGです。
文字数が限られている中で複数の強みに触れると、それぞれのエピソードが浅くなり、結局どの強みも説得力をもって伝えられなくなります。
最も自信があり、かつ志望企業にマッチする強み一つに絞り、それを深く掘り下げる方が、結果的に強く印象に残ります。
【強み別】就活の自己PR例文15選
ここからは、いよいよ具体的な例文を紹介していきます!
自分の強みに合った例文を参考にすることで、自己PRを書くときの参考にしてくださいね。
例文1:主体性
私の強みは、目標達成のために現状を分析し、自ら課題を設定して行動できる「主体性」です。
所属していたテニスサークルでは、新入生の定着率の低さが課題でした。例年は練習についていけない新入生が夏休み前に半数脱落していましたが、私は全員でサークル活動を楽しみたいと考えました。
そこで、新入生一人ひとりにヒアリングを行い、「練習のレベルが高すぎること」「先輩との交流が少ないこと」が原因だと特定しました。
解決策として、実力別の練習メニューと、先輩後輩がペアを組むダブルスの練習日を新設することを提案し、自ら企画・運営を行いました。
その結果、今年度の新入生の脱落者はゼロになり、サークル全体の活気が増しました。
この経験で培った主体性を活かし、貴社に入社後は現状に満足することなく、常に課題を見つけ改善していくことで、チームの目標達成に貢献したいです。
例文2:協調性
私の強みは、多様な意見を持つメンバーをまとめ、一つの目標に向かわせる「協調性」です。
大学のグループワークで、文化祭の出店企画を担当した際、メンバー間で意見が対立し、議論が停滞してしまいました。
私はまず、全員の意見を丁寧にヒアリングし、それぞれの考えの背景にある想いや懸念点を理解することに努めました。
その上で、各意見の共通点である「来場者に楽しんでもらいたい」という目的を再確認し、それぞれの案の長所を組み合わせた新しい企画を提案しました。
具体的には、「インスタ映え」を重視するAさんの案と「手軽さ」を重視するBさんの案を融合させ、「片手で持てるカラフルなスイーツ」を販売しました。結果、商品はSNSで話題となり、準備した300食が2日間で完売しました。
貴社でも、この協調性を発揮し、様々なバックグラウンドを持つチームメンバーと協力しながら、プロジェクトを成功に導きたいと考えております。
例文3:継続力
私の強みは、目標達成のために地道な努力をこつこつと続けられる「継続力」です。
私は大学入学時にTOEICで900点を取るという目標を立て、毎日2時間の英語学習を3年間継続しました。具体的には、朝1時間は単語学習、通学中に30分のリスニング、夜30分は文法問題と決め、1日も欠かさず実行しました。
モチベーションが下がりそうな時は、英語の映画を字幕なしで見るなど楽しみながら学習を続ける工夫をしました。その結果、入学時に550点だったスコアを、大学3年の冬には目標であった920点まで伸ばすことができました。
この経験で培った継続力と計画性は、貴社の業務においても、長期的な視点が必要なプロジェクトを着実に遂行し、目標を達成する上で必ず役立つと確信しております。
例文4:課題解決力
私の強みは、現状を分析して課題の原因を突き止め、解決策を実行できる「課題解決力」です。
アパレルのアルバイトで、ECサイトの売上が伸び悩んでいるという課題がありました。
私は社員の方に許可をいただき、アクセスデータを分析したところ、サイト訪問者の多くが特定の商品ページを見た後に離脱していることを発見しました。
原因を探るため、お客様アンケートを実施した結果、「商品のサイズ感が分かりにくい」という声が多数挙がりました。
そこで、身長別のスタッフ着用画像と、より詳細なサイズガイドを各商品ページに追加することを提案し、写真撮影からサイト更新まで担当しました。
結果、ページの離脱率は20%改善し、ECサイト全体の売上は3ヶ月で前年比130%を達成しました。
この課題解決力を活かし、貴社でもデータに基づいた的確な現状分析を行い、事業成長に貢献していきたいです。
例文5:傾聴力
私の強みは、相手の話に真摯に耳を傾け、言葉の裏にある本質的なニーズを引き出す「傾聴力」です。
スマートフォンの販売員としてアルバイトをしていた際、あるご年配のお客様が「操作が難しくて使いこなせない」と相談に来られました。
私はただ操作方法を説明するのではなく、まずはお客様がスマートフォンで何をしたいのか、どんなことに困っているのかを1時間かけてじっくりお聞きしました。
その結果、「お孫さんとビデオ通話がしたい」という本当の想いを引き出すことができました。
そこで、ビデオ通話アプリに特化した使い方マニュアルを自作し、文字の大きさや表現を工夫してお渡ししたところ、「あなたのおかげで孫の顔が見られた」と大変喜んでいただけました。
貴社の営業職においても、この傾聴力を発揮し、お客様が本当に求めていることを的確に捉えることで、最適な提案を行い、深い信頼関係を築いていきたいです。
例文6:計画性
私の強みは、目標達成から逆算して綿密な計画を立て、着実に実行する「計画性」です。
大学祭の実行委員として、10チームが参加するステージ企画の責任者を務めました。過去には準備不足で本番にトラブルが多発していたため、私はまず全体のスケジュールを1ヶ月前から1日単位で作成しました。
そして、各チームの役割とタスク、締め切りを明確にした進捗管理シートを導入し、週1回の定例会で進捗を確認・共有する体制を整えました。
準備が遅れているチームには個別でヒアリングを行い、人員を追加するなどしてサポートしました。
この計画的な進行管理により、すべてのチームが余裕を持って準備を終え、本番では一つのトラブルもなく、来場者アンケートで満足度95%という高評価を得ることができました。
この計画性を活かし、貴社のプロジェクトマネジメント業務においても、納期と品質を守り、チームの成果を最大化することに貢献できると確信しています。
例文7:柔軟性
私の強みは、予期せぬ事態にも臨機応変に対応できる「柔軟性」です。
所属するアカペラサークルで、野外ライブイベントを企画した際、本番当日にメインスピーカーが故障するというトラブルが発生しました。開演まで1時間を切り、パニックになるメンバーもいましたが、私はまず落ち着いて代替案を考えました。
会場の管理者に交渉して予備の小型スピーカーを2台お借りし、マイクの音量を調整することで、会場後方のお客様にも歌声が届くようにセッティングを変更しました。
また、急遽MCの時間を設け、お客様に状況を正直にお伝えし、一体感を高める工夫をしました。結果として、機材トラブルを乗り越え、ライブを無事に成功させることができ、お客様からも温かい拍手をいただきました。
仕事においても不測の事態は起こりうると思いますが、この柔軟性を活かして、どんな状況でも冷静に最善策を判断し、粘り強く業務を遂行していきたいです。
例文8:リーダーシップ
私の強みは、チームの目標達成に向けてビジョンを示し、メンバーの士気を高める「リーダーシップ」です。
私はサッカー部の副キャプテンとして、チームを県大会ベスト4に導きました。当初、チームは練習試合で連敗が続き、士気が低下していました。私はキャプテンと相談し、「全員が主体的に関わるチーム」を目指すことを提案しました。
具体的には、練習メニューをトップダウンで決めるのではなく、ポジションごとに選手自身が課題を分析し、練習内容を考えるように変更しました。
また、週に一度「Goodプレー共有会」を開き、互いの良いプレーを褒め合う場を設けました。
これにより、選手一人ひとりに当事者意識が芽生え、チームの一体感が向上しました。結果として、チームの守備力は格段に上がり、目標であった県大会ベスト4を達成できました。
この経験で培ったリーダーシップを、貴社でもチームの目標達成に貢献するという形で発揮していきたいと考えています。
例文9:責任感
私の強みは、任された役割を最後までやり遂げる「責任感」の強さです。
私は大学の図書館でアルバイトをしており、学生が返却した本を書架に戻す「配架」業務を担当していました。この業務は単純作業ですが、1冊でも間違えると利用者が本を見つけられなくなる重要な役割です。
ある日、蔵書点検で5冊の配架ミスが発覚し、私は自分の仕事の重大さを痛感しました。それ以来、ミスをゼロにすることを目標に、独自のチェックリストを作成し、作業前後で二重確認を徹底しました。
また、間違いやすい書籍のパターンを分析し、他のスタッフにも共有することで、チーム全体のミス削減に努めました。
その結果、半年後の蔵書点検では配架ミスをゼロにすることができ、職員の方から「君のおかげで助かった」という言葉をいただきました。
貴社に入社後も、この責任感を持って一つ一つの業務に真摯に取り組み、周囲から信頼される人材になりたいです。
例文10:行動力
私の強みは、目標達成のために失敗を恐れず、まず行動に移すことができる「行動力」です。
私は大学で地域活性化に関心を持ち、「地元の商店街の魅力をSNSで発信する」という個人プロジェクトを立ち上げました。
当初はフォロワーが10人程度で全く影響力がありませんでしたが、私はまず商店街の全店舗に足を運び、店主の方々に直接取材を申し込みました。
断られることもありましたが、30店舗以上を取材し、お店の歴史やこだわりを記事にして投稿し続けました。
また、フォロワーを増やすために、地域のイベントに積極的に参加してチラシを配ったり、他の地域メディアと連携したりしました。
こうした地道な行動を1年間続けた結果、フォロワーは5000人を超え、メディアで紹介されたお店の売上が1.5倍になるなどの成果に繋がりました。
この行動力を活かし、貴社でも新規顧客開拓などのチャレンジングな業務において、臆することなく積極的にアプローチし、成果を出していきたいです。
例文11:分析力
私の強みは、複雑な情報の中から本質的な課題を見つけ出す「分析力」です。
私はマーケティングのゼミで、あるフリーペーパーの発行部数減少の原因を探るという課題に取り組みました。
チームの皆は「SNSの普及が原因だ」と推測しましたが、私はより客観的な根拠が必要だと考え、過去5年間の読者アンケートと発行部数のデータを分析しました。
その結果、部数減少の主な原因は、メイン読者層であった40代の満足度低下にあることを突き止めました。
さらにアンケートを深掘りすると、彼らが求める「地域のディープな情報」が減り、ありきたりな店舗紹介が増えたことに不満を感じていることが分かりました。
この分析結果を基に、企画内容の見直しを提案し、高く評価されました。
貴社に入社後も、この分析力を活かして市場や顧客のデータを的確に読み解き、事業戦略の立案に貢献したいと考えています。
例文12:チャレンジ精神
私の強みは、困難な目標や未経験の分野にも、成長の機会と捉えて積極的に挑戦する「チャレンジ精神」です。
私は大学3年生の時、プログラミング未経験ながら「学内の履修管理を効率化するWebアプリを開発する」という目標を立て、挑戦しました。
まずは独学でプログラミング言語の学習を始め、オンライン教材や書籍を活用して毎日3時間勉強しました。
開発過程では、エラーが解決できず何日も悩むこともありましたが、諦めずにオンラインコミュニティで質問したり、情報系の学部の友人に助言を求めたりして乗り越えました。
半年の試行錯誤の末、友人50人が利用してくれるアプリを完成させることができ、大きな達成感を得ました。この経験から、困難な課題でも粘り強く取り組むことの重要性を学びました。
貴社が挑戦を歓迎する社風であると伺い、このチャレンジ精神を活かして、前例のない業務にも果敢に取り組み、会社の成長に貢献したいです。
例文13:誠実さ
私の強みは、誰に対しても、どんな状況でも、真摯に向き合う「誠実さ」です。
コンビニエンスストアでアルバイトをしていた際、私がレジ操作を誤り、お客様に本来より500円多く請求してしまうというミスを犯しました。お客様が店を出た後にミスに気づき、私はすぐに店長に報告しました。
店長は「気づかないお客様もいるから…」と言いましたが、私は自分の過ちから逃げたくない一心で、防犯カメラの映像からお客様を探し出すことをお願いしました。
幸いにも常連のお客様であったため連絡先が分かり、謝罪の上で返金することができました。後日、そのお客様から「正直に話してくれてありがとう。これからもこの店を利用するよ」というお言葉をいただき、誠実な対応が信頼に繋がることを実感しました。
社会人としても、この誠実な姿勢を貫き、お客様や社内の仲間から信頼される人間として、貴社に貢献したいと考えています。
例文14:粘り強さ
私の強みは、一度決めた目標は最後まで諦めずにやり遂げる「粘り強さ」です。
私は大学で所属する陸上部で、長距離走の選手として活動していました。大学2年の時に足を故障し、半年間走れない時期がありました。
仲間が記録を伸ばしていく中で焦りを感じ、競技を辞めることも考えました。しかし、「必ず復帰して自己ベストを更新する」という目標を諦めきれず、リハビリに専念しました。
医師やトレーナーと相談しながら、体幹トレーニングや筋力強化など、今できることに全力で取り組みました。
地道な努力を続けた結果、怪我を乗り越え、最後の大会では自己ベストを30秒更新することができました。この経験から、困難な状況でも目標を見失わずに努力し続けることの重要性を学びました。
この粘り強さを活かし、仕事で困難な壁に直面しても、最後まで諦めずに解決策を探し続け、貴社の事業に貢献したいです。
例文15:調整力
私の強みは、利害関係が異なる人々の間に入り、双方にとって納得のいく着地点を見つける「調整力」です。
私は大学の演劇サークルで、舞台監督を務めました。その際、演出家が求める芸術性の高い舞台装置と、制作担当者が主張する予算や安全性の確保という点で意見が対立しました。
板挟みになった私は、まず双方の意見を個別にじっくりと聞きました。そして、両者が「良い舞台を作りたい」という共通の目標を持っていることを確認した上で、三者での会議の場を設けました。
会議では、私が中立的な立場で進行役を務め、演出家には予算内で実現可能な代替案を、制作担当者には安全性を確保しつつも演出家の意図を汲んだ設計を提案しました。
粘り強く対話を重ねた結果、双方が納得する形で舞台を完成させることができ、公演を成功に導きました。
この調整力を、社内外の様々な関係者と連携することが求められる貴社の業務において活かし、円滑なプロジェクト推進に貢献したいです。
【エピソード別】就活の自己PR例文5選
アルバイトやサークルといった身近な経験も、伝え方次第で立派な自己PRになります。
「こんな普通の経験でいいのかな?」と不安に思う必要はありません。
ここでは、就活の自己PRの例文をエピソード別に解説していきます。
どんなエピソードならOK?
結果の大小にかかわらず、「あなたの強みや人柄が発揮された経験」であれば、どんなエピソードでも自己PRのネタになります。
企業は、あなたが経験したことの「すごさ」を競わせたいわけではありません。むしろ、課題にどう向き合ったか、チームでどう動いたかといった、仕事の場面を想起させるエピソードを評価します。
サークル、ゼミ、研究、アルバイト、インターン、留学など、どんな経験でも大丈夫です。
大切なのは、「すごさ」ではなく、仕事でも活かせる強みであることを伝えることなのです。
例文1:アルバイト(飲食店)
私の強みは、現状の課題を発見し、改善のために周囲を巻き込みながら行動できる「課題解決力」です。
個人経営のカフェでアルバイトをしていた際、ランチタイムの行列が原因でお客様を逃してしまうことが課題でした。私は店長に「事前注文システムの導入」を提案しました。
当初、店長はコスト面から難色を示しましたが、私は無料のツールを複数調査し、操作方法のマニュアルも自主的に作成して再度提案しました。私の熱意が伝わり、試験的な導入が決定しました。
他のアルバイトスタッフにも操作方法をレクチャーし、協力を仰ぎました。結果、お客様の待ち時間が平均10分短縮され、回転率が1.5倍に向上。ランチタイムの売上は前月比で120%を達成しました。
この経験のように、現状に満足せず、より良くするための方法を考えて実行する力は、常に変化する市場に対応する必要がある貴社の業務においても必ず活かせると考えております。
例文2:サークル活動
私の強みは、目標達成のために綿密な計画を立て、チームを率いることができる「計画性」と「リーダーシップ」です。
私は音楽サークルの新歓担当として、新入生を30人入部させるという目標を掲げました。例年の課題であった「イベント後の入部率の低さ」を解決するため、私は2つの施策を実行しました。
第一に、新歓イベントを従来の演奏会だけでなく、楽器体験会や部員との交流会など複数回に分け、新入生との接触機会を増やしました。
第二に、参加者リストを作成し、イベント後には個別でメッセージを送るなど、丁寧なフォローを徹底しました。
これらの計画的なアプローチの結果、例年の倍となる40人の新入生が入部し、目標を大幅に達成することができました。
この経験から、目標達成のためには事前の計画と丁寧な実行が不可欠であることを学びました。貴社においても、この計画性を活かして着実に業務を遂行し、成果に繋げたいです。
例文3:ゼミ・研究
私の強みは、困難な課題に対しても諦めずに仮説と検証を繰り返す「粘り強さ」です。
私は社会学のゼミで「若者の投票率の低下」というテーマで卒業論文を執筆しました。当初、先行研究を調べる中で、ありきたりな結論しか出せずに執筆が行き詰まってしまいました。
しかし、私は諦めずに、自分なりの視点を見つけるため、実際に大学生100人を対象とした独自のアンケート調査と、20人への対面インタビューを実施しました。
その結果、「政治への不信感」だけでなく「投票所の物理的な遠さや時間の制約」が投票行動の大きな障壁になっているという新たな仮説を立てることができました。
この一次情報に基づいた論文は教授から高く評価され、ゼミの優秀論文として選ばれました。
この研究活動で培った粘り強さと探究心を、貴社のマーケティングリサーチ業務において、顧客の深層心理を的確に捉え、新たなニーズを発掘するために活かしたいです。
例文4:長期インターンシップ
私の強みは、現状を分析し、改善策を実行する「課題解決力」です。
私は大学3年生の時に、ITベンチャー企業で6ヶ月間の長期インターンシップに参加し、自社メディアのSNS運用を担当しました。当初、アカウントのフォロワー数は500人で伸び悩んでいました。
私はまず、競合他社のアカウントを30社以上分析し、投稿時間やコンテンツ内容、ハッシュタグの使い方を徹底的に研究しました。
その分析結果から、ターゲットである20代女性には「共感を呼ぶイラストコンテンツ」が有効であると仮説を立て、社員の方に提案し、コンテンツ作成の許可を得ました。
自らイラストレーターと交渉し、週に3回のコンテンツ投稿を実行した結果、3ヶ月でフォロワー数は3000人まで増加し、Webサイトへの流入数を2倍にすることができました。
このインターンシップで培った課題解決力を活かし、貴社でも常に現状を分析し、より良い成果を出すための改善提案を積極的に行っていきたいです。
例文5:留学経験
私の強みは、多様な文化や価値観を持つ人々と積極的にコミュニケーションをとり、信頼関係を築くことができる「異文化適応力」です。
私は大学2年生の時に、1年間カナダへ語学留学しました。当初は英語がうまく話せず、現地の学生の輪に入ることができませんでした。
この状況を打破するため、私は日本文化を紹介するイベントを自主的に企画し、学生寮の友人を招待しました。折り紙や書道を通じて交流する中で、少しずつ自分のことを理解してもらえるようになり、会話の機会も増えていきました。
また、現地のNPO団体でボランティア活動に参加し、様々なバックグラウンドを持つ人々と協働する中で、文化の違いを乗り越えて一つの目標に向かうことの面白さを学びました。
最終的には、国籍の異なる10人以上の友人ができ、彼らと共に行ったプロジェクトは今でも最高の思い出です。
この留学経験で培った異文化適応力とコミュニケーション能力は、グローバルに事業を展開する貴社で、海外のクライアントやチームメンバーと協業する際に必ず活かせると考えています。
まとめ
本記事では、以下の内容をお伝えしました。
- 自己PRは、自分の強みを会社でどう活かすか伝えることが大切
- 自己PRには、自己分析と企業研究が欠かせない
- 構成やコツを押さえれば、良い自己PRが書ける
- バイトやサークルを自己PRに書いても良い
就活の自己PRは、自分の強みを入社してどう活かすことができるかアピールする場のことです。
自己PRを書けるようになるには、自己分析と企業分析の両方をすることが大切です。
自己PRを書くときは、最初に強みを一文で言い切るなどの、正しい構成を意識するようにしましょう。
この記事が、参考になれば幸いです。
人気記事