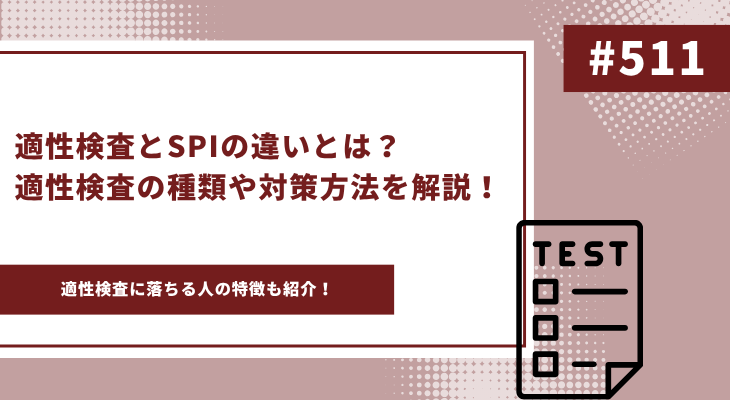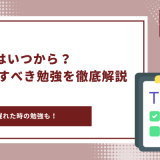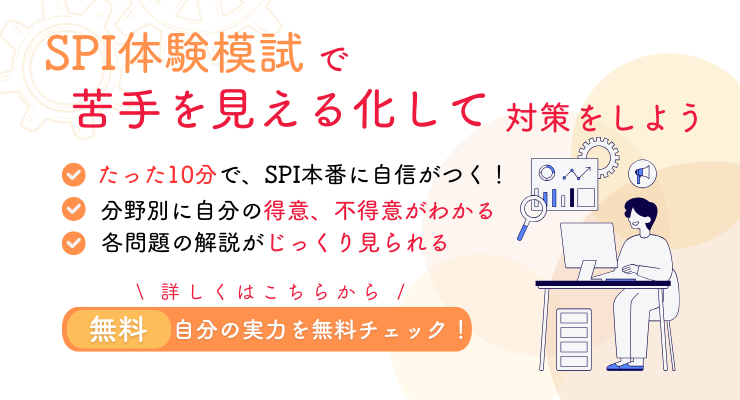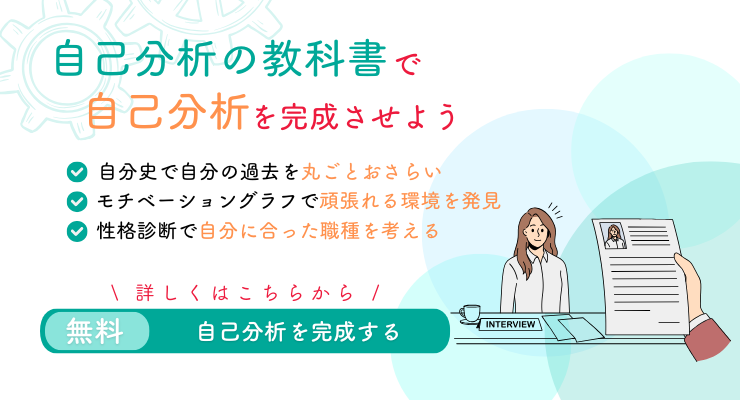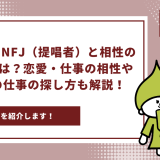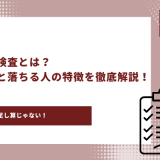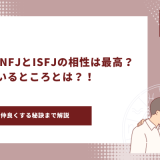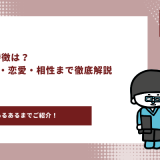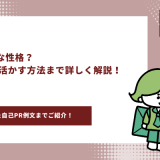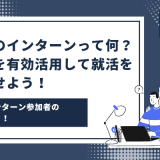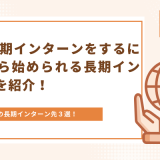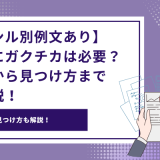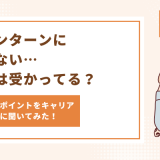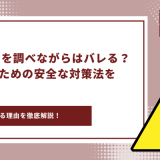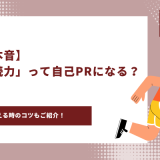就職活動を進める中で、「適性検査」や「SPI」という言葉をよく耳にしても、その違いがいまいちわかっていない人も多いのではないでしょうか?
この記事では、適性検査とSPIの違いだけでなく、SPI以外の主要なテストの種類や具体的な対策方法まで、解説していきます。
この記事を最後まで読めば、適性検査に対する不安を自信に変え、万全の準備で選考に臨めるようになるでしょう。
こんな人に読んでほしい
- 「適性検査」と「SPI」の違いが曖昧な人
- SPI以外のテストの種類についても知りたい人
- 適性検査を通過するための具体的な方法が知りたい人
適性検査とは?
「適性検査」とは、企業が応募者の能力や人柄を把握するために実施するテストのことをいいます。
短い面接だけでは見抜けない応募者の潜在的な能力や、自社の社風に合うかをデータに基づいて判断するために、多くの企業で使われています。
単なる選考の足切りとしてだけでなく、①客観的な人物理解、②入社後のミスマッチ防止、③内定後の配属先決定や人材育成の参考資料として、企業にとって非常に重要な役割を果たしているのです。
SPIとは?
では、よく聞く「SPI」とは何なのでしょうか。
SPIはリクルート社が開発した、日本で最も利用されている適性検査です。
つまり、「適性検査」という大きな枠組みの中に「SPI」という種類のテストがある、という関係性になっています。これが適性検査とSPIの違いなのです。
年間利用社数は18,100社以上、受検者数は257万人にも上るため、就活生が最初に対策すべき最重要テストと言えるでしょう。
SPIの対策方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてくださいね!
SPIの「能力検査」とは?
SPIの能力検査は、会社で働くときに共通して求められる、基礎的な知的能力を測るテストです。
どのような仕事でも情報を正しく理解し、論理的に考える力が必要です。そのため、企業は学生に能力検査を課すことで、そうした大切な能力が備わっているかどうかを確認しています。
内容は「言語分野(国語)」と「非言語分野(数学)」の2つで構成されています。
難易度は中学~高校レベルで、基礎的な学力があれば解ける問題が中心ですが、時間が非常にタイトなので対策は必須です。
SPIの内容がわかっても、どのような問題が出題されるのか、わからない学生の方も多いのではないでしょうか。
SPI体験模試では、実際にSPIで頻出の問題を、本番さながらの時間配分で体験することができます。
無料で短時間で模試を受けられるので、ぜひ一度模試を受けてみてくださいね!
SPIの「性格検査」とは?
SPIの性格検査は、応募者の人柄や考え方の傾向を把握し、企業との相性を見るための検査です。
性格検査には、企業文化や職務への適性を客観的に判断し、入社後のミスマッチを防ぐ目的があります。
検査の形式は、約300問の質問に対し、直感的に回答していくというものになります。
ここで注意したいのが、回答の一貫性から嘘を見抜く「ライスケール」という仕組みがあることです。
自分を偽って良く見せようとすると、回答に矛盾が生じて信頼性を失うため、正直に答えることが何よりも重要です。
性格検査を通過した先輩の体験談
ここでは、自己分析を丁寧にしたことで性格検査を通過することができた先輩の体験談を紹介します。
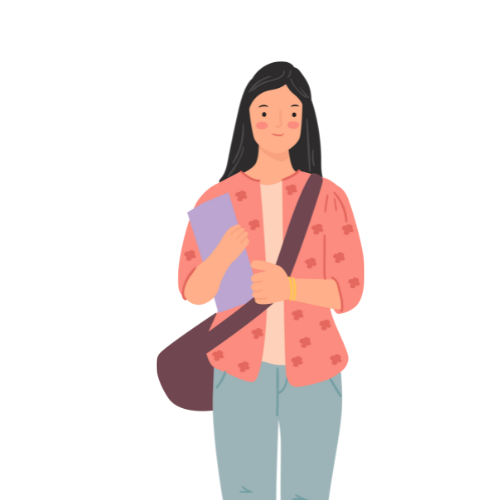
私は、就活を始めたばかりの時、「企業に合わせるべきか、でも嘘はバレるって聞くし…」と、性格検査の回答に悩んでいたんです。そんな時、性格検査に回答するためには、自己分析をすることが効果的であると知りました。
そこで、自己分析を進めるために、『自己分析の教科書』を使ってみました。
手順通りに過去の経験や自分の価値観を深掘りしていくうちに、自分の強みや弱み、価値観などがわかるようになりました。
その後の本番の性格検査では、もう迷いはありませんでした。 自分という軸が定まっていたので、どんな質問にも自信を持って、一貫性のある回答ができました。
事前に自己理解を深めておくだけで、こんなに安心してテストに臨めるとは思いませんでした!
性格検査で、一貫性のある回答をするためには自己分析が欠かせません。
「自己分析の教科書」では、手順に沿って項目を埋めていくだけで、就活で必要な自己分析を完結させることができます。
Aさんも、自己分析をしっかりとしたことで、性格検査でも自信を持って回答することができるようになりました。
性格検査に困っている人や、自己分析のやり方がよくわかっていない人は、ぜひ「自己分析の教科書」を利用してみてくださいね!
SPIの種類と形式
SPIには対象者別の「種類」と、受検場所別の「形式」があります。
企業は採用したい人物像や選考フローに応じてこれらを使い分けているため、自分が受けるSPIの種類と形式を正しく把握しておくことが大切です。
SPIの種類には、以下のようなものがあります。
- SPI-H
高校生向け。高卒採用で使われている。 - SPI-U
新卒向け。短大卒から大学院卒まで幅広く使われている。 - SPI-G
社会人向け。中途採用の場面で使われている。
SPIの形式には、以下のようなものがあります。
- テストセンター
指定会場のPCで受検。最も一般的な形式。 - Webテスティング
自宅のPCで受験。電卓が使えるが、前の問題に戻れない。 - ペーパーテスト
企業が用意した会場でマークシート形式で受検。 - インハウスCBT
応募先企業のPCで受検。珍しい形式。
SPI以外の主要な適性検査
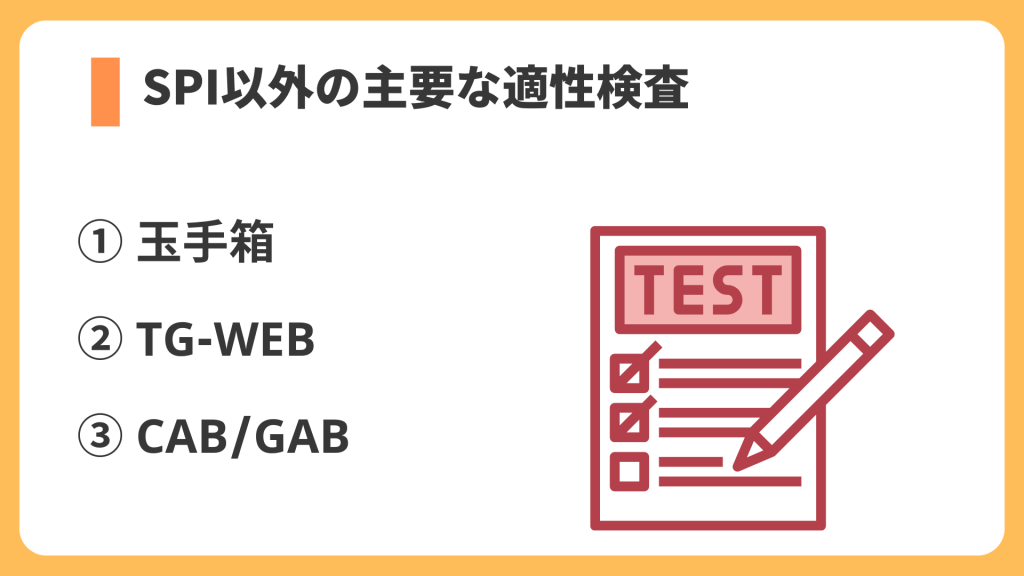
実は、企業が採用する適性検査はSPIだけではありません。
SPI以外にも「玉手箱」「TG-WEB」「CAB/GAB」など、複数の適性検査が存在します。
特に金融やコンサル、IT業界ではSPI以外のテストが頻出するので、SPI対策だけでは志望企業に対応できない可能性があります。
志望業界が定まっていない人は、主要なテストの特徴を知っておくことで、幅広い業界の適性検査に対応できるようにしましょう。
玉手箱
玉手箱は、時間制限が非常に厳しいのが特徴です。
問題数に対して制限時間が極端に短く、1問あたり数十秒で解答する必要があるため、処理能力の速さと正確性が求められます。
最大の特徴は、同じ形式の問題が連続して出題される点です。
金融業界やコンサルティング業界など、スピードと正確性を重視する企業で多く採用されています。
TG-WEB
TG-WEBは、ユニークで難易度が高いことが特徴です。
従来の学力試験とは異なる、未知の問題に対する思考力や問題解決能力を測ることを目的としています。
暗号解読や図形の展開図など、初見では解き方が分かりにくい問題が多い「従来型」と、問題は簡単だがスピードが求められる「新型」の2種類があります。
コンサル業界や外資系企業などで導入される傾向があります。
CAB/GAB
CABとGABは、特定の職種や業界への適性を測ることに特化したテストです。
CABはIT職(SE・プログラマー)に必要な情報処理能力や論理的思考力を、GABは総合商社などで求められる知的能力を測るために作られています。
特にCABは、暗号や命令表といったプログラミングの思考プロセスに近い問題が出題されるため、IT業界を目指すなら対策が欠かせません
適性検査で落ちる人の共通点
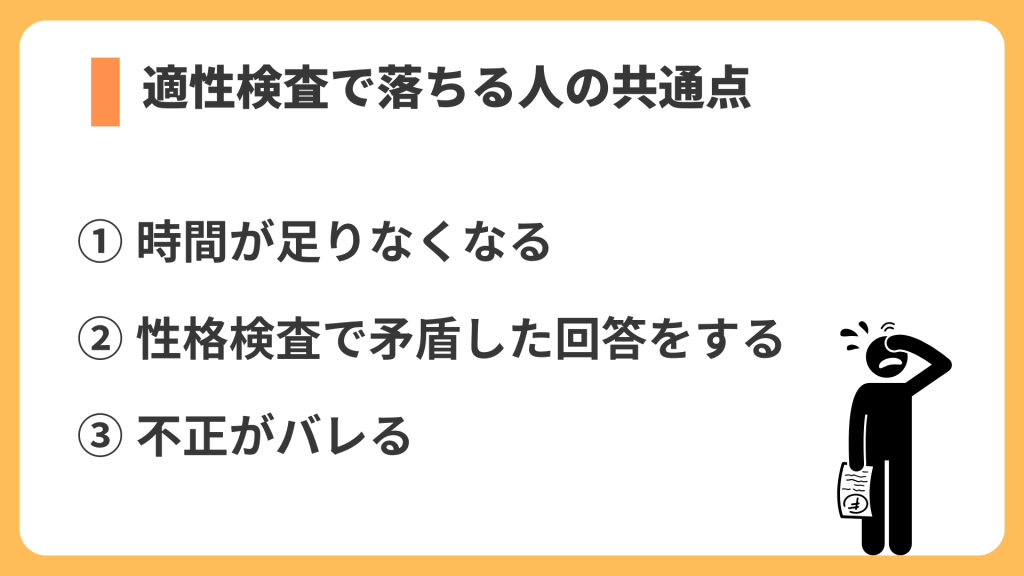
「時間不足」「性格検査の矛盾」「不正の発覚」が、適性検査で落ちる主な原因です。
適性検査は学力だけでなく、時間管理能力や自己理解の深さが求められるため、これらの点に課題があると通過することは難しいです。
多くの学生が陥りがちな失敗パターンを知り、事前に適性検査の対策に役立てていきましょう。
時間が足りなくなる
一番多い失敗が、時間配分を意識せず、時間切れになってしまうケースです。
適性検査は問題数に対して制限時間が短く設定されており、全問をじっくり解くことは想定されていません。
対策として、普段から1問1分など時間を計って解く練習をすることが効果的です。
また、適性検査本番では、少し考えて分からなければすぐに次の問題に進む勇気も必要ですよ。
性格検査で矛盾した回答をする
自分を良く見せようと嘘をつくと、回答に矛盾が生じ、信頼性を失ってしまいます。
性格検査には、同じ内容を異なる聞き方で質問し、回答の一貫性をチェックする「ライスケール」が組み込まれているため、矛盾は簡単に見抜かれてしまいます。
事前に自己分析を徹底し、自分の価値観や性格を深く理解しておけば、自身の回答に一貫性を持たせることができるでしょう。
不正がバレる
最近増えている監視型Webテストでの不正行為は、AIと人間の目によって高い確率で発覚します。
PCのカメラを通じて受験中の視線や行動、周囲の音などがリアルタイムで監視・記録されており、不審な動きはAIが検知して企業に報告される仕組みになっているんです。
替え玉受験やカンニングなどの不正が横行したため、企業側も対策を強化しています。
公正な選考を受けるためにも、クリーンな環境で、実力で臨むことが絶対条件です。
そもそも適性検査対策は必要?
「自分は対策しなくても大丈夫かも?」と思っていることはありませんか?
基本的には全員に対策を推奨しますが、一部、短時間の準備で済む学生もいるのは事実です。
しかし、適性検査は独特の出題形式と厳しい時間制限があるため、元々の学力だけでは高得点が難しいことが多いです。
まずは自分の実力を把握し、必要な対策量を見極めることが重要になります。
対策が少なくて済む人の特徴
では、どんな人が少ない対策で済むのでしょうか。
それは、「基礎学力が非常に高い人」と「情報処理速度に自信がある人」です。
- 特徴① 基礎学力が高い
共通テストの国語や数学で8割以上取れる人 - 特徴② 処理速度が速い
計算や読解の速さに自信がある人
しかし、上記のような特徴に自分が合っているのかわからない人も多いですよね。
自分が適性検査の対策をするべきかわからない人は、一度「SPI体験模試」を受けてみましょう。
無料で短時間で、自分の実力を確認できるので、ぜひ試してみてくださいね!
少しでも不安なら対策するのが吉
自分が対策不要かどうかの判断に迷ったら、迷わず対策を始めましょう。
対策をしすぎて損をすることはありませんが、対策不足で早期選考の機会を失うことは本当にもったいないです。
多くの就活生が適性検査に対策をしてから臨んでいます。「自分は大丈夫」という油断が、思わぬ損失に繋がることも少なくありません。
適性検査を通過するための5ステップ
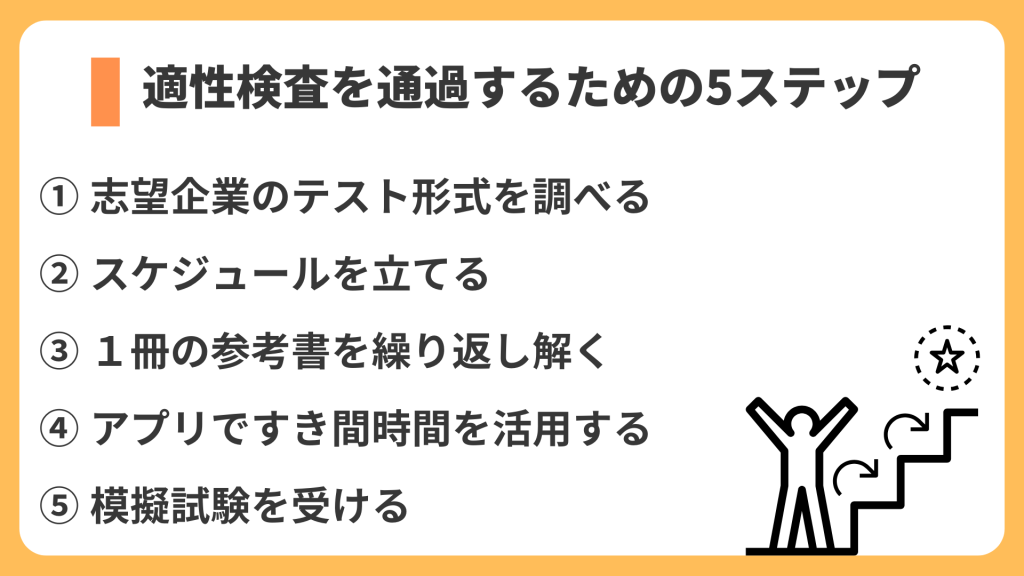
ここからは、いよいよ具体的な対策方法です。
計画的な準備と実践的な練習が、適性検査を突破するために欠かせません。
やみくもに勉強を始めるのではなく、志望企業に合わせて戦略を立て、効率的に学習することで、限られた時間の中で最大限の成果を出すことができます。
以下の5つのステップで対策を進めることで、どんなテストにも対応できる実力が身につきます。
Step1: 志望企業のテスト形式を調べる
最初に行うべきは、志望企業が過去にどの適性検査を導入したかの情報収集です。
対策すべきテストの種類を特定することで、学習範囲を絞り、効率的な対策が可能になります。
就活サイトの選考体験記や、大学のキャリアセンター、OB・OG訪問などを活用して情報を集めましょう。
特に第一志望群の企業が使うテストは最優先で対策するようにしましょう。
Step2: スケジュールを立てる
収集したテストの情報に基づき、最も早いテスト日から逆算して学習計画を立てます。
就活はES作成や面接対策など他にもやることが多いため、計画的に進めないと時間が不足してしまいます。
一般的に、対策には30~60時間必要と言われています。
最も早い本番の3ヶ月前から、1日1時間程度の学習時間を確保するのが理想的です。
Step3: 1冊の参考書を繰り返し解く
複数の参考書に手を出すのではなく、信頼できる1冊を完璧にマスターすることが重要です。
1冊を繰り返すことで、問題の出題パターンや解法が定着し、解答のスピードと正確性が向上します。
まずは時間を計らずに一通り解き、自分の実力と苦手分野を把握します。
その後、間違えた問題を重点的に、解き方を覚えるまで何度も反復練習しましょう。
Step4: アプリでスキマ時間を活用する
通学中などのスキマ時間を活用して、アプリで問題演習を行いましょう。
毎日少しでも問題に触れることで、知識の定着と解答スピードの向上ができます。
特に、暗記が必要な言語の語彙問題や、非言語の公式確認などに最適です。
手軽に実力アップが図れるので、ぜひ活用してみてください。
Step5: 模擬試験を受ける
学習の総仕上げとして、本番同様の環境で模擬試験を受けましょう。
時間制限というプレッシャーの中で問題を解く経験を積むことで、本番での焦りを減らし、実力を最大限に発揮できるようになります。
模擬試験の中でもおすすめなのが、「SPI体験模試」です!
SPI体験模試では、本番さながらの時間配分で、SPIに挑戦することができます。
これまでの勉強がどれくらい自分に身についたのか確認するためにも、ぜひ挑戦してみてくださいね!
SPI体験模試はこちら
まとめ
本記事では、以下の内容をお伝えしました。
- 適性検査の中の一つにSPIがある
- SPIは、能力検査と性格検査に分かれている
- 適性検査には、玉手箱やTG-WEBなど多くのテストがある
- 志望企業で出題されるテストの対策をすることが大切である
今回は、適性検査とSPIの違いから、主要なテストの種類、具体的な対策法まで解説しました。
適性検査とSPIの違いを正しく理解し、計画的に対策を進めることがとても大切です。
適性検査は単なる足切りではなく、あなたと企業の相性を見るための重要なプロセスです。
その重要性を認識し、十分な準備をすれば、自信を持って選考に臨め、内定獲得に大きく近づくことができるでしょう!
人気記事