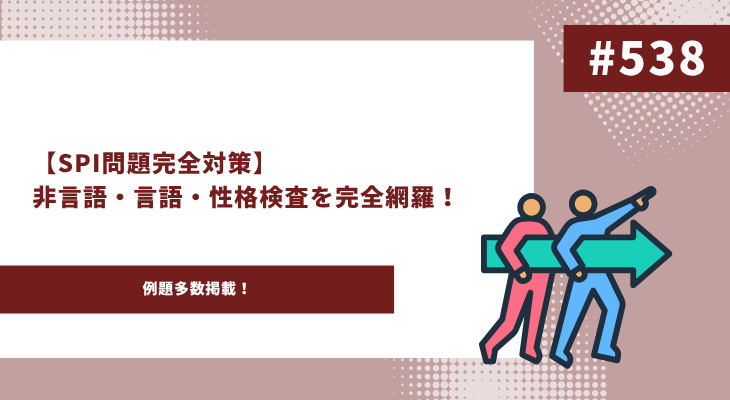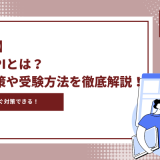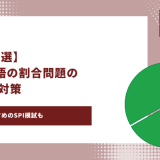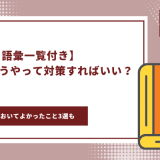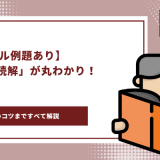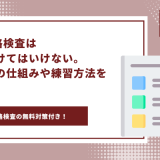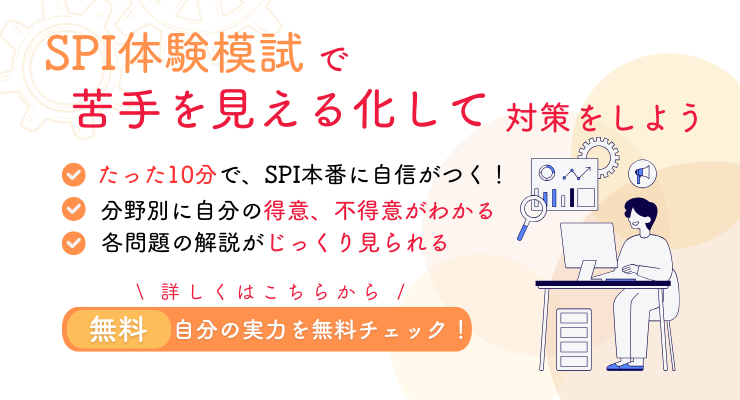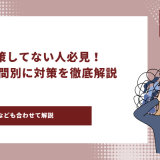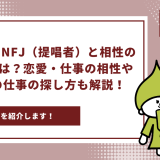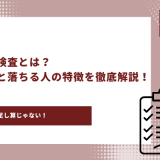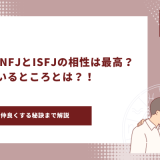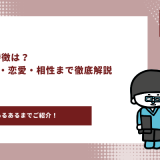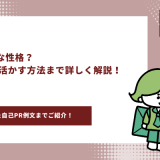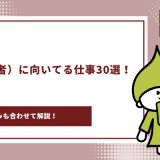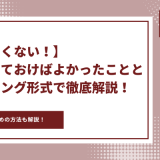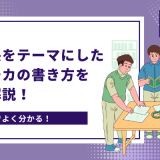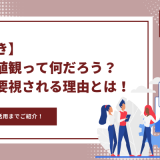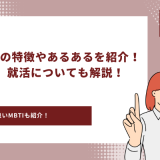就職活動で多くの企業が最初の関門として導入しているSPI。
「SPIの問題ってどんな内容?」「対策したいけど、何から手をつければいいか分からない」と不安に感じている就活生も多いのではないでしょうか。
この記事では、SPIで出題される問題の種類や形式を、豊富な例題とともに徹底解説します。
言語・非言語・性格検査の各分野における頻出問題の解き方のコツから、効率的な勉強法、おすすめの対策ツールまで、SPI対策に必要な情報をすべて詰め込みました。
こんな人に読んで欲しい!
- SPIの問題形式や内容が分からず不安な方
- 効率的なSPIの勉強方法を知りたい方
- 言語・非言語・性格検査の具体的な対策を知りたい方
SPIとは?就活の第一関門

SPIは、多くの企業が採用選考で利用する、個人の能力と人柄を測るための適性検査です。能力検査と性格検査の2つで構成されており、就活における最初の関門と言えます。
企業はSPIを通じて、応募者が業務に必要な基礎的な知的能力を持っているか、また自社の社風に合う人材かを見極めています。入社後のミスマッチを防ぎ、採用の効率化を図るという目的があるのです。
なぜ企業はSPI問題を出す?
企業がSPIを導入する主な理由は「能力の足切り」「人柄のマッチング」「面接の参考資料」の3つです。
人気企業には多数の応募者が集まるため、全員と面接することは不可能です。そのため、SPIの結果で一定の基準を満たした学生に絞り込んだり、性格検査の結果から自社に合いそうな人材を見つけたりしています。
例えば、論理的思考力が重要な職種では非言語のスコアを重視します。また、性格検査で「チームで協力する」傾向が出た学生には、面接でチームでの経験を深掘りするなど、人物理解のための参考資料としても活用されます。
SPI問題の4つの受検形式
SPIには「テストセンター」「WEBテスティング」「ペーパーテスティング」「インハウスCBT」の4つの受検形式があります。
志望企業がどの形式を採用しているか事前に確認することが重要です。
なぜなら、受検形式によって、出題傾向や問題数、電卓の使用可否などが異なるため、対策方法が変わってくるからです。
例えば、テストセンターは1問ごとに制限時間があり、前の問題に戻れないという特徴があります。
- テストセンター: 指定会場のPCで受検。最も一般的な形式。
- WEBテスティング: 自宅のPCで受検。電卓使用が前提の問題も出る。
- ペーパーテスティング: 企業が用意した会場でマークシート形式で受検。
- インハウスCBT: 企業のオフィスでPCを使って受検する形式。
SPIの受験方式については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
SPI非言語の頻出問題と例題
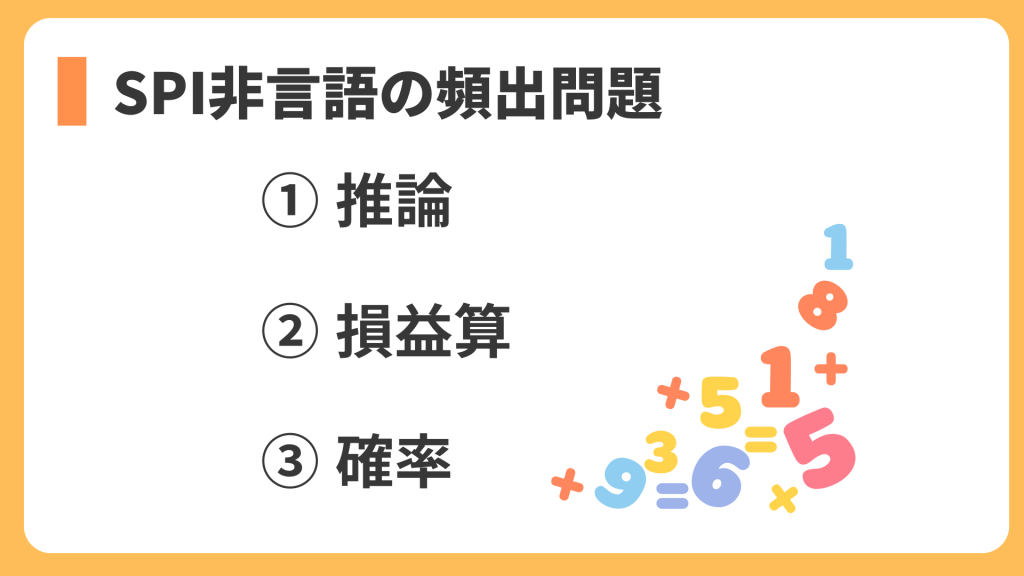
非言語は、中学・高校レベルの数学知識を基にした論理的思考力や数的処理能力を測る問題です。問題自体は難解ではありませんが、速く正確に解くスピードが求められます。
多くの問題が出題されるのに対し、試験時間が短く設定されているため、1問あたり1分程度で解く必要があります。そのため、公式の暗記と解法パターンの習得が不可欠です。
SPI頻出問題①:推論
推論は、与えられた複数の条件から論理的に正しい結論を導き出す問題です。情報を図や表に整理して、矛盾なく当てはまるものを見つけるのが攻略の鍵です。
文章で与えられた条件は複雑に見えるため、頭の中だけで解こうとすると混乱しがちです。図式化することで、情報を視覚的に整理でき、関係性を正確に把握できます。
問題:
Aさん、Bさん、Cさんの3人が会議に出席した。
- Aさんが出席した場合、Bさんも必ず出席する。
- Bさんが出席しない場合、Cさんは出席しない。
- Cさんは出席した。
Aさんは出席したか?
解答:Aさんが出席したかどうかはわからない。
解説:
- 「Aさんが出席すればBさんも出席する」という条件は、「A ⇒ B」という関係を表す。
- 「Bさんが出席しなければCさんも出席しない」という条件は、「¬B ⇒ ¬C」です。これを対偶にすると「C ⇒ B」になる。つまり、Cさんが出席すれば必ずBさんも出席するという意味。
- 実際にCさんが出席しているので、「C ⇒ B」によりBさんも出席していることがわかる。
しかし、Bさんが出席しているからといってAさんが出席しているとは限らない。条件①は「Aが出席すればBも出席する」という片方向の関係なので、Bが出席していてもAが出席しているかどうかは判断できない。
SPI頻出問題②:損益算
損益算は、商品の仕入れや販売に関する利益や割引を計算する問題です。
「原価」「定価」「売値」「利益」の関係性を正しく理解し、公式に当てはめて解きます。
ビジネスの基本である損益計算の感覚を測る問題であり、用語の定義を混同すると正しく計算できません。
特に「〇割の利益を見込む」「定価の〇割引」といった表現を正確に式にすることが重要です。
問題:
ある商品の価格がまず20%値下げされた後、さらに10%値下げされた。元の価格が10,000円のとき、最終的な販売価格はいくらか?
解答:7,200円
解説:
まず、10,000円 × 0.8(=20%引き)= 8,000円
次に、8,000円 × 0.9(=10%引き)= 7,200円
SPI頻出問題③:確率
確率は、ある事象が起こる可能性を分数や割合で求める問題です。「全体の場合の数」と「該当する事象の場合の数」をそれぞれ正確に数え上げることが基本です。
SPIの確率問題は、中学数学レベルの基本的な問題が中心です。しかし、「くじを引いて元に戻すか戻さないか」など、条件を一つ読み間違えるだけで答えが変わるため、注意深い読解力が必要です。
問題:
公平なコインを同時に3回投げる。表が少なくとも2回出る確率を求めよ。
解答:1/2
解説:
全事象は 2^3=8通り。
表がちょうど2回出るのは3 通り、ちょうど3回出るのは1通り。
よって確率は 、(3+1)/8=4/8=1/2
SPIの非言語問題をさらに対策したい方には、こちらの記事がおすすめです。
SPI言語の頻出問題と例題
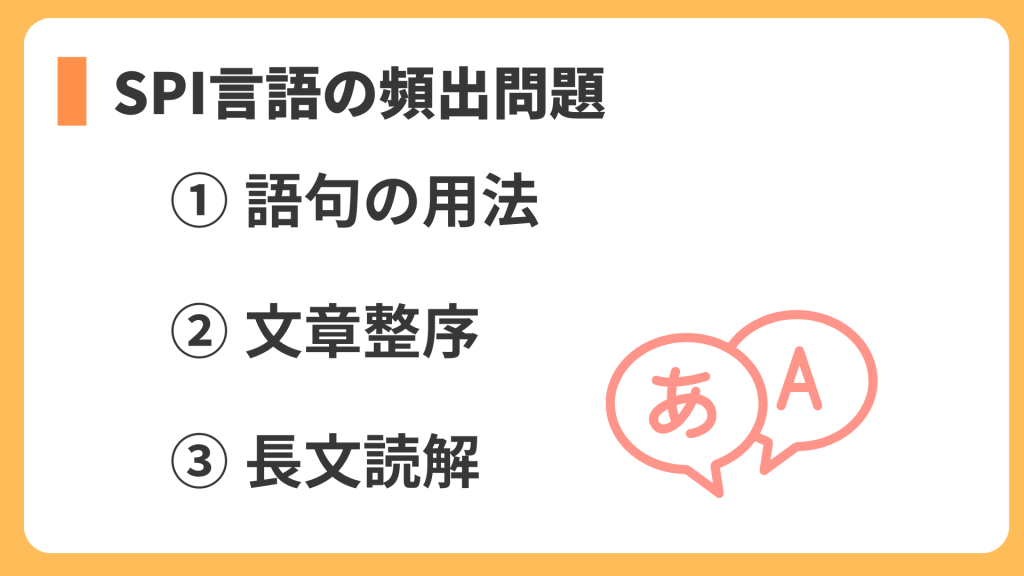
言語は、言葉の意味や文章の構造を正確に理解する能力を測る、国語の問題です。語彙力と読解力が問われ、非言語と同様に解答スピードが重要になります。
約30〜40問を30分程度で解く必要があり、1問にかけられる時間は1分未満です。そのため、問題形式に慣れ、頻出語句を暗記しておくことが高得点への近道です。
SPI頻出問題①:語句の用法
語句の用法は、問題文で示された単語と最も近い意味で使われている選択肢を選ぶ問題です。単語を別の言葉に言い換えてみると、意味が明確になり解きやすくなります。
日本語には同じ言葉でも文脈によって意味が変わる多義語が多く存在します。この問題では、文脈に応じた適切な意味を把握できているかが試されます。
問題:
次の二語の関係と同じ関係にあるものを、A〜Dから1つ選びなさい。
「鍵」: 「錠」
A. 筆 : 紙
B. 医者 : 診察
C. 質問 : 回答
D. 弁 : 蝶番(ちょうつがい)
解答:D
解説:
「鍵」と「錠」は、互いに組み合わさって機能を果たす道具の関係。Dの「弁」と「蝶番」も、扉の開閉という機能のために組み合わさって使われる道具の関係。
他の選択肢は手段と目的、行為と結果など関係が異なる。
語句問題の対策法は、こちらの記事でも解説しています。
SPI頻出問題②:文章整序
文章整序は、バラバラにされた選択肢の文を、意味が通るように正しく並べ替える問題です。接続詞や指示語(「しかし」「そのため」「これ」など)に着目するのが解法のコツです。
接続詞や指示語は、文と文の論理的な関係性を示しています。これらをヒントにすることで、話の因果関係や時系列を効率的に組み立てることができます。
問題:
次のア〜エの文を意味の通るように並べ替えたとき、正しい順番を選びなさい。
ア. また、作業効率が向上するため、社員の残業時間も削減できる。
イ. 最近、当社では新しい業務管理システムを導入した。
ウ. これにより、進捗状況やタスクの優先度を一目で把握できるようになった。
エ. その結果、プロジェクト全体の管理が容易になった。
- イ → ウ → エ → ア
- イ → ア → ウ → エ
- ウ → イ → エ → ア
- イ → ウ → ア → エ
解答:1
解説:
冒頭は状況の説明から入るのが自然 → 「イ」が最初(新システム導入)。
次に、そのシステムの効果を説明 → 「ウ」が続く(進捗や優先度を把握できるようになった)。
その結果、プロジェクト管理が容易になった → 「エ」。
最後に、さらに派生的な効果(残業削減)を述べる → 「ア」。
よって イ → ウ → エ → ア が自然な流れ。
SPI頻出問題③:長文読解
長文読解は、文章を読んで内容を理解し、設問に答える問題です。先に設問を読み、文章中の何を探すべきかを把握してから本文を読むと効率的です。
設問には「空欄に当てはまる接続詞を選べ」「筆者の主張に最も近いものを選べ」といった形式があります。答えは必ず本文中にあるため、自分の知識や推測で判断しないことが重要です。
問題:
近年、多くの企業が「働き方改革」を掲げ、在宅勤務やフレックスタイム制度を導入している。その目的は、生産性の向上やワークライフバランスの改善にある。しかし、制度を導入するだけでは十分ではない。社員が制度を活用しやすい環境や企業文化を整えることが、真の改革につながる。例えば、上司が率先して在宅勤務を活用することで、部下も安心して制度を利用できるようになる。逆に、制度があっても職場に暗黙の出社圧力が残っていれば、改革は形骸化してしまうだろう。
筆者が最も強調していることはどれか。
A. 在宅勤務は生産性向上に効果がある。
B. 働き方改革は制度導入だけでは不十分である。
C. 上司が在宅勤務を活用すべきではない。
D. 出社圧力は企業文化を改善する。
解答:B
解説:
文章全体の主張は、「制度導入だけでは不十分で、利用しやすい環境・文化の整備が必要」という点。AやCは部分的な事例、Dは本文内容と逆の意味。
こちらの記事では、SPIの長文読解問題に特化して解説してるので、併せて参考にしてみてください。
SPI性格検査の問題と対策
性格検査は、約300問の質問を通じ、応募者の人柄や行動特性を測る検査です。正解はなく、自分を偽らず正直に、かつ一貫性を持って回答することが最も重要です。
企業は、自社の文化や求める人物像と応募者の特性が合っているかを見ています。嘘の回答をすると、類似の質問への回答と矛盾が生じ、「虚偽の回答をする人物」と判断され、かえって評価を落とす可能性があります。
性格検査で落ちる人の特徴
性格検査で落ちやすいのは「回答に一貫性がない」「嘘をついて自分をよく見せようとする」「極端な回答ばかりする」人です。これらの回答は、信頼性や協調性に欠けると判断されるリスクがあります。
性格検査には、同じ内容を異なる表現で尋ねる質問が含まれており、回答の矛盾をチェックしています。また、全ての質問に「全くあてはまる」や「全くあてはまらない」といった極端な回答をすると、柔軟性がない、あるいは自己中心的な印象を与えてしまう可能性があるので注意が必要です。
SPIの性格検査についてもっと詳しく知りたい方は、こちの記事をご覧ください。
SPI性格検査の戦略的対策
性格検査の最適な対策は「①自己分析で自分の軸を固める」「②企業の求める人物像を理解する」の2ステップです。
まず自分の性格や価値観を理解していないと、質問に対してブレのない一貫した回答ができません。その上で、企業の社風を把握し、それに合致する自分の側面をアピールすることが、ミスマッチを防ぎ、通過率を高めることにつながります。
まずは、こちらの自己分析の教科書などを活用して、自分の強みや価値観を言語化してみましょう。こちらのシートをフォーマット通りに埋めて行けば、面倒な自己分析も簡単に終わらせることができますよ。
自己分析シートを利用するにはこちらをクリック
先輩のSPI問題・体験談
SPIで苦労した先輩たちも、正しい対策で乗り越えています。具体的な失敗談と成功体験から、効果的な対策のヒントを学びましょう。
ここでは、非言語問題でつまずいた先輩と、ESとSPIの両立に悩んだ先輩の2つの体験談を紹介します。
非言語問題で焦ったAさんの話
Aさん(商学部)は、得意だと思っていた非言語の推論問題で大失敗しました。しかし、問題集で解法パターンを徹底的に叩き込むことで、苦手意識を克服しました。
学校の数学とは違うSPI特有の問題形式に、本番で戸惑ってしまったのが失敗の原因でした。特に推論問題は、解き方の「型」を知っているかどうかが、解答スピードに直結します。

最初の受検では、推論問題の条件を整理できずに時間が過ぎ、頭が真っ白になりました。その後、SPIの対策本を1冊買い込み、特に推論問題を図や表に書き出して解く練習を繰り返しました。この『可視化』する癖をつけたことで、次のテストでは落ち着いて解けるようになりました。
ESと両立したBさんの話
Bさん(文学部)は、性格検査の対策と、膨大なES作成との両立に悩んでいました。AIツールでES作成を効率化し、捻出した時間をSPI対策に充てることで、両方の選考を突破しました。
就職活動では、SPI対策だけでなく、自己分析、ES作成、面接対策など、やるべきことが山積みです。賢くツールを活用して時間を捻出することが、選考突破の鍵になります。

性格検査で矛盾した回答をしないように、自己分析シートで自分の考えを整理しました。一番大変だったのはES作成の時間でしたが、AIでES作成をサポートしてくれる『SmartES』を友人に勧められ、活用したところ、ES作成時間を大幅に短縮できました。その浮いた時間でSPIの問題演習に集中できたことが、合格につながったと思います。
SmartESを利用するにはこちらをクリック
効率的なSPI問題の勉強法
SPIの効率的な勉強法は「①1冊の問題集を完璧にする」「②苦手分野を潰す」「③時間を計って解く」の3つです。やみくもに手を広げるより、一つの教材を繰り返し解く方が効果的です。
まずは問題集を1周して、自分の苦手分野(推論、長文読解など)を把握します。次に、その苦手分野を重点的に2周、3周と繰り返し解き、解法パターンを体に染み込ませましょう。通学中などのスキマ時間には、無料アプリで語彙問題などを解くのもおすすめです。
また、力試しにSPI体験模試を受けてみるのもおすすめです。
SPIの受験まで時間がない!という方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
まとめ:SPI問題を攻略して内定へ
- SPIは能力と人柄を測るテスト。正直さと一貫性が大事。
- 言語・非言語ともに時間との勝負。問題形式に慣れることが最優先。
- 1冊の問題集を繰り返し解き、苦手分野をなくすのが効率的。
SPIは、正しい知識と十分な対策があれば、決して乗り越えられない壁ではありません。
今日から計画的に学習を始め、自信を持って本番に臨みましょう。
SPIは多くの企業が採用する重要な選考ステップですが、その評価基準は明確です。本記事で紹介したSPI問題の傾向と解き方のコツを理解し、練習を重ねることで、必ず結果はついてきます。
人気記事