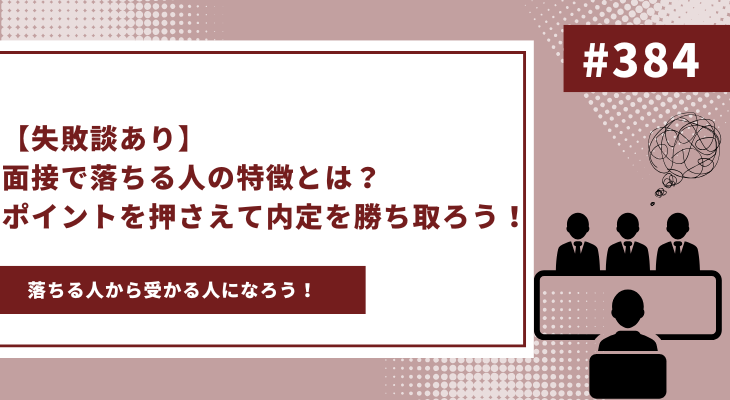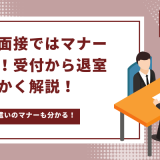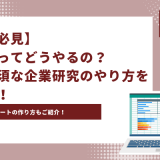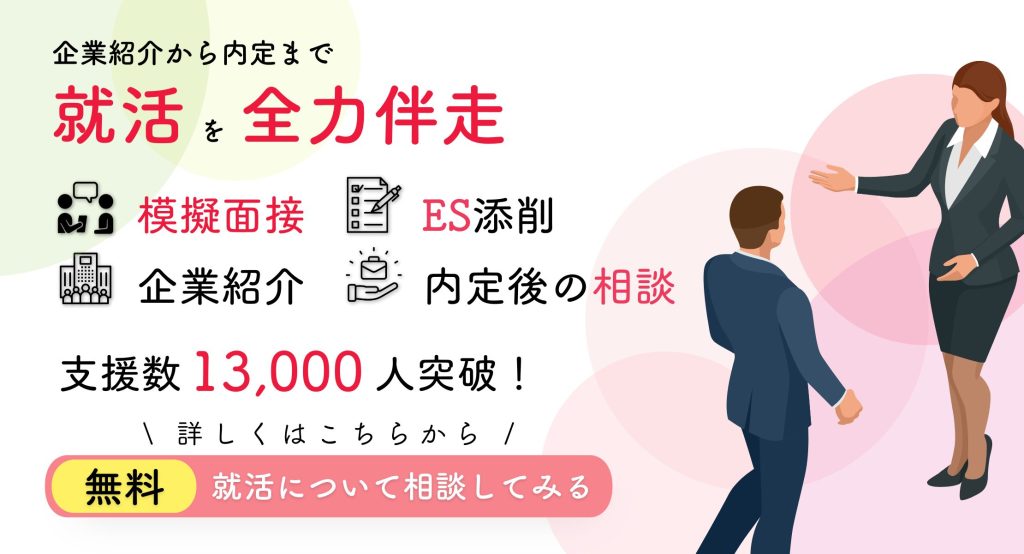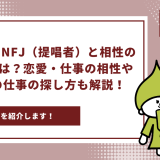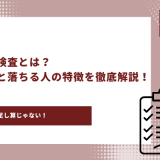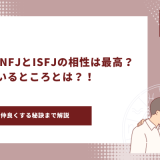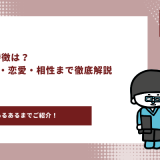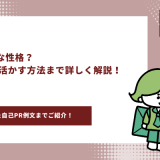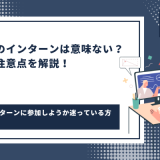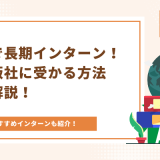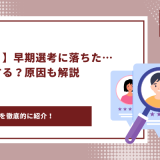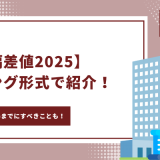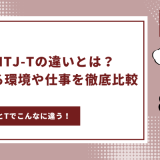就活を行なっていく上で、面接に落ちてしまい自信がなくなってしまうという悩みは多いのではないでしょうか。何社もの面接を受けて、なかなか面接を通過しないと不安を抱いてしまうのも当然ですよね。
そこで、本記事では面接に落ちる人の特徴について解説し、その対処法も併せて紹介します。次に活かすためにも、面接における自分の弱点を知っておくことは非常に重要です。
見落としがちな面接のポイントをおさえて、次の面接で合格をもらえるようにしましょう。
こんな人に読んでほしい
- 面接で落ちる人の特徴を知りたい方
- 面接で企業が重視するポイントを知りたい方
- 就活生の面接での失敗談を知りたい方
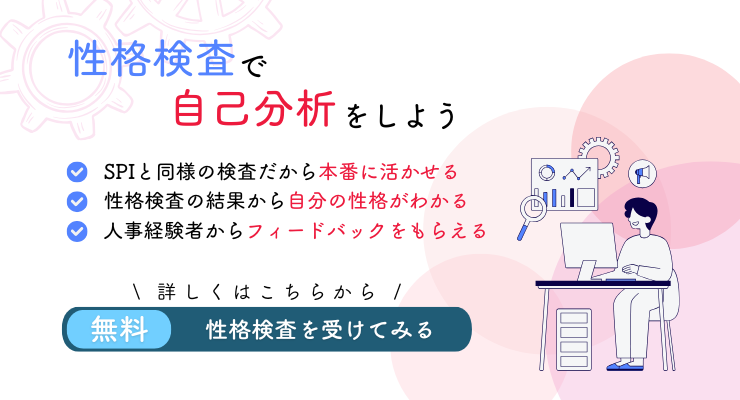
性格検査を上手く利用して、自己分析を進めましょう!SPIマスターでは、本番同様の性格検査を受けることができます。また、基本的にSPIは結果が確認することのできないですが、SPIマスターではそのSPIと同様の結果を確認することができます!
そのため、性格検査の結果から簡単に自己分析をすることができます!
「自己分析をやりたいけどどうやってやればいいのかわからない…」「性格検査の結果を用いて自己分析をしたい!」という方は、「SPIマスター」を申し込むことをおすすめします!
SPIマスターの特徴は以下の通りです。
- SPIと同様の検査だからそのまま本番に活かせる!
- 性格検査の結果から自分の性格が客観的に把握できる!
- 人事目線での結果に対するフィードバックを受けられる!
結果を確認できるからこそ、自己分析を効率的に進めることができます。
「SPIマスター」の申し込みはこちらから!
面接で落ちる人はどのくらいいる?

実際、面接で落ちる人はどのくらいいるのでしょうか?ここでは、面接で落ちる人の割合について詳しく紹介します。
一次面接で落ちる人の割合
一次面接で落ちる人の割合は、30%程度であると言われています。一次面接では、応募者の基本的な適性が見られています。具体的には、志望動機・自己PR・コミュニケーション能力・企業とのマッチ度などが評価の対象です。ここで基準に達しないと判断された場合、不採用となる確率が高いです。
面接で落ちる主な理由として、志望動機が曖昧・自己PRが弱い・受け答えが不明瞭・企業研究不足などが挙げられます。それだけでなく、話し方や態度、表情といった印象面も非常に重要な判断材料です。
一次面接を突破するには、事前準備を徹底し、企業の求める人物像を理解した上で受け答えすることが大切です。
二次面接で落ちる人の割合
二次面接で落ちる人の割合は一般的に50%程度とされています。企業によっては半数以上が不採用となる場合もあります。
二次面接では、一次面接を通過した応募者の中から、さらに企業の求める人物像に合致するかどうかを詳しく判断されます。具体的には、「専門性やスキル」「志望動機の深堀り」「実際の業務への適性」「社風とのマッチ度」が評価対象となります。また、企業側が「最終面接に進めるほどではない」と判断した場合も不採用となるでしょう。
二次面接を突破するには、論理的かつ具体的な受け答えを意識し、企業への理解を深めることが重要である。
三次面接で落ちる人の割合
三次面接(最終面接前)で落ちる人の割合は40%程度とされています。二次面接を通過した時点で、応募者のスキルや適性は一定の評価を受けているが、最終的な選考基準に達しない場合、不採用となります。
三次面接では、「企業文化への適合度」「リーダーシップや将来性」「意思決定力」「入社意欲」がより厳しく見られます。特に、役員クラスの面接官が参加することが多く、企業の価値観や経営方針に合うかが重要視される傾向にあります。
三次面接は複数名が最終面接に進むため、企業側が最適な人材を最終的に厳選する段階となります。三次面接を突破するには、企業のビジョンを理解し、長期的な貢献意欲を示すことが鍵となるでしょう。
最終面接で落ちる人の割合
最終面接で落ちる人の割合は、50%程度とされています。最終面接は基本的に「採用するかどうか」の判断が下される場ですが、全員が内定を得られるわけではありません。
最終面接で落ちる主な理由には、「企業の文化や価値観との不一致」「他の候補者との比較」「最終決定者の評価」などがあります。また、スキルや経験は十分でも、熱意やコミュニケーション能力の不足が影響することもあります。
特に倍率の高い人気企業では、最終面接でも厳選が行われるため、落ちる確率が高くなります。一方で、人手不足の業界では、最終面接通過率が高くなることもあります。
最終面接に臨む際には、自分の強みが企業の求める人材像とどのようにマッチするか具体的に伝えるようにしましょう。
面接で落ちる人の特徴とは?

面接で落ちる人にはいくつかの共通の特徴がある場合が多いです。まずは、自分の弱点を知るところから始めましょう。
【マナー編】面接で落ちる人の特徴
基本的なマナーが身についていない人は面接で落ちる可能性が高くなります。基本的なマナーというのは、以下のようなものが挙げられます。
・遅刻
・服装の乱れ
・挨拶ができていない
・言葉遣いのミス
・態度の悪さ
面接で第一印象は非常に重要で、最初の数秒で評価が決まることもあります。どれだけ優秀でも、社会人としての基本的な礼儀ができていないと、企業からの評価は下がってしまうでしょう。
面接の際には、「感じの良い印象」を意識して臨むようにしましょう。
【受け答え編】面接で落ちる人の特徴
面接官からの質問に対して、適切な受け答えができなければ評価は下がってしまいます。受け答えが適切でない人の特徴を以下に挙げているので、ぜひ参考にしてください。
・質問の意図を理解していない
・回答が的外れ
・結論が曖昧
・話が長すぎる
面接官の質問に対し、簡潔に要点を伝えられないと「論理的思考力がない」と判断されてしまう可能性があります。また、「志望動機は特にありません」「なんでも挑戦したいです」といった熱意が伝わらない回答もマイナス要素となってしまいます。
面接を突破するためには、質問の意図を理解し、簡潔かつ具体的に自分の強みや熱意を伝えることを意識しましょう。
【内容編】面接に落ちる人の特徴
面接官は、面接での応募者の話の質を重視しています。面接官は多くの人を審査しなければならないため、印象に残らない内容であれば、選考を通過するのが難しくなってしまうでしょう。
面接に落ちてしまいやすい人の特徴を以下に挙げます。
・自信がない
・熱意が伝わらない
・ありきたりな内容
・自己分析ができていない
・自己PRが弱い
自信がない人は「声が小さい」「目線が定まらない」「話し方が曖昧」といった特徴があり、面接官にネガティブな印象を与えてしまいます。さらに、熱意が伝わらない人や内容がありきたりな人は面接官の印象に残りづらく、魅力が伝わりにくい傾向があります。事前に自分の経験を振り返り、エピソードを整理するようにしましょう。
また、自己分析ができていない人は「強みや弱みが説明できない」「過去の経験をうまく言語化できない」といった特徴があり、説得力に欠けることがあります。自己分析を行うと自分自身を理解することができ、それらが自信につながります。
自己分析を行ったことがない人は、ぜひ一度行ってみてください。
自己分析シートを利用するにはこちらをクリック
【オンライン編】面接に落ちる人の特徴
最近では、オンライン面接を取り入れている企業が多くあります。オンライン面接において、環境やコミュニケーションの準備不足などは減点の対象となってしまいます。オンライン面接は対面面接とは異なり、画面越しで好印象を与える工夫をする必要があります。オンライン面接での主な問題点として、以下のようなものが挙げられます。
・通信トラブル
・音声や映像の乱れ
・カメラ映りの悪さ
・暗い表情
・視線が合わない
・話し方が聞き取りにくい
特に、通信環境が不安定で途中で途切れると、スムーズなやり取りができず評価が下がってしまいます。また、「カメラを見ずに話す」「リアクションが薄い」「姿勢が悪い」などの態度で面接に臨んでしまうと、面接官に「意欲が低い」「自信がない」というマイナスな印象を与えます。
オンライン面接を成功させるには、安定した通信環境を確保し、明るい表情、はっきりとした話し方を意識することが重要です。
面接で受かる人の特徴とは?
ここまで、面接で落ちる人の特徴について解説してきましたが、面接に受かる人にはどのような特徴があるのか知りたいですよね。面接に受かる人の特徴から、面接の必勝法を攻略していきましょう。
面接官を惹きつける
面接で受かる人は、面接官を惹きつける「話し方」と「文章構成」を意識しています。面接というのは自分をアピールする場であるため、自分の話に興味を持ってもらうことは非常に重要です。面接官が自分の話に興味を持ってくれれば、話しやすい環境でアピールすることができ、面接を楽しむことができるでしょう。
面接官は「この人と一緒に働きたいか」を判断するため、自分らしさを出しつつ、企業にどう貢献できるかを明確に伝えることを意識すようにしましょう。
企業が重視するポイントを理解している
企業は、単に優秀な人材を求めているのではなく、自社の価値観や方針に合った人材を採用したいと考えています。そのため、受かる人は自分の強みや経験と企業の求める人物像を結びつけてアピールすることを意識しています。
例えば、企業が「主体性」を重視している場合、過去に自ら考えて行動し、成果を出した経験を具体的に話すことで、企業のニーズに合う人材であると伝えることができます。
面接では、事前に企業研究を行い、何を重視しているのかを理解した上で、自分の強みとどうマッチするかを明確に伝えることを意識しましょう。
面接で印象を左右すると言われがちな“沈黙”ですが、実際は合否を決めるものではありません。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
参考:面接での沈黙はアウト?不安だけど合格もある?|面接官が本音で回答│転職参謀
面接で企業が重視する3つのポイント
企業は面接において、3つのポイントを重視しています。企業の求める人物像を理解して、面接に臨みましょう。
コミュニケーション能力
面接において企業が重視するポイント1つ目は、コミュニケーション能力です。仕事をする上で、コミュニケーション能力が高いことは非常に大切です。
企業は、質問に対して「的確に答えられるか」「論理的に話せるか」「相手の話をきちんと聞けるか」といった点をチェックしています。結論が曖昧だったり、話が長すぎたりすると、相手に伝わりにくくマイナス評価につながります。
面接では、簡潔かつわかりやすい回答を意識し、相手の目を見て話すことを心がけましょう。
企業との相性
面接で企業が重視するポイント2つ目は、自社との相性です。企業はスキルや経験だけでなく、「この人が社風やチームに馴染めるか」を見ています。
どんなに優秀でも、企業との相性が悪ければ、長く活躍することは難しいです。そのため、面接官は応募者の考え方や人柄、コミュニケーションの取り方を注意深くチェックしています。相性をアピールするためには、企業研究をしっかり行い、自分の価値観や働き方と企業がどのようにマッチしているかを伝えることが重要です。
無理に企業に合わせようとするのではなく、自分に合った会社かどうかを見極めることも大切です。
成長意欲
面接で企業が重視するポイント3つ目は、成長意欲です。企業は、入社後の活躍を期待できる人材を求めています。そのため、面接では「新しい知識を学ぶ姿勢があるか」「困難を乗り越える姿勢をもっているか」などが見られています。
例えば、過去に挑戦した経験や、努力して成長したエピソードを話すことで、前向きに努力する姿勢をアピールできます。また、入社後のビジョンを具体的に伝えることも重要です。入社をゴールと考えず、常に前進していく姿勢をアピールすることができます。
逆に、「指示されたことだけをやればいい」という受け身の姿勢では、企業に魅力を感じてもらえません。業界や職種について事前に学び、成長意欲があることを伝えることを意識しましょう。
面接の質問については以下もご覧ください。
参考:【面接官必見!】採用面接の質問内容とは?「本当に良い人材」を見抜く質問例100選|即戦力RPO
就活生に聞いた!面接に落ちた際の失敗談
ここでは、実際の就活生に聞いた面接での失敗談を紹介します。
私が以前、第一志望の企業の面接で不採用となった際の失敗談をご紹介いたします。一次面接は無事に通過し、二次面接に進みましたが、その場で思うように力を発揮できませんでした。
第一の失敗は、企業研究が不十分だったことです。面接官から「当社の強みは何だと思いますか?」と質問されましたが、表面的な情報しか知らず、具体的にお答えすることができませんでした。その結果、「本当に当社に興味があるのか?」と疑問を持たれた可能性がございます。
第二の失敗は、自己PRが抽象的だったことです。自分の強みとして「コミュニケーション能力が高い」とお伝えしましたが、具体的なエピソードを交えなかったため、説得力に欠けてしまいました。
第三の失敗は、受け答えに自信がなかったことです。緊張してしまい、目をそらしながら話したり、声が小さくなったりしたことで、面接官に「自信がない」と思われたかもしれません。
この経験を通じて、事前準備の重要性と、自信を持って具体的にお話しする大切さを学びました。
面接に落ちる人が合格をもらう秘訣

上記で、面接に落ちる人の特徴を紹介しましたが、面接で合格をもらうためには実際どんな対策を行えばいいのでしょうか。ここでは、面接に落ちる人がやるべき対策を具体的に紹介します。
身だしなみを整える
面接では、スーツを着用することが基本ですが、スーツの着方や髪型、清潔感などもみられていることを意識しましょう。志望動機や面接での態度に気を取られて、服装を後回しにしてしまう方も多いですが、身だしなみは面接での第一印象に大きな印象を与えます。
香水のつけすぎや靴の汚れなど、細かい部分もチェックされることがあるため、気を抜かないようにしましょう。面接前には鏡でチェックし、身だしなみの最終確認をすることがおすすめです。
自己分析を行う
面接で落ちる人は、自己分析を行うようにしましょう。自己分析を行うことで、自分の強みや弱みを明確にし、企業に対して説得力のある自己PRや志望動機を作成することができます。
また、自己分析で自分の意外な一面にも気付くことができ、それらが自信にもつながるでしょう。さらに、自己分析を通じて、自分の課題や成長過程を把握することができるため、面接官からの意図せぬ質問にも落ち着いて対応できます。
自己分析を行ったことがない方も、行ったことがある方も今一度自分を見つめ直してみましょう!
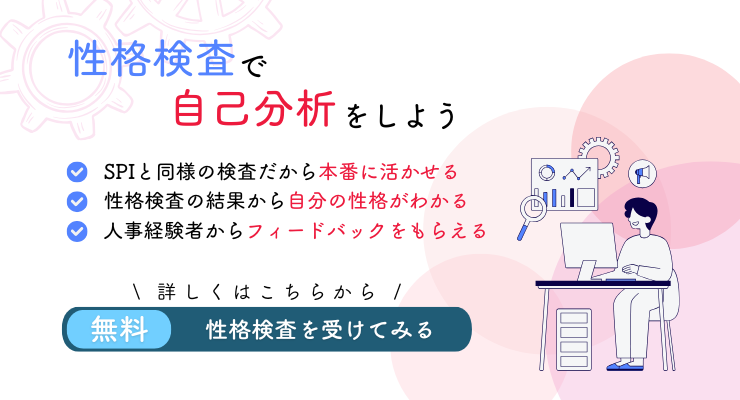
性格検査を上手く利用して、自己分析を進めましょう!SPIマスターでは、本番同様の性格検査を受けることができます。また、基本的にSPIは結果が確認することのできないですが、SPIマスターではそのSPIと同様の結果を確認することができます!
そのため、性格検査の結果から簡単に自己分析をすることができます!
「自己分析をやりたいけどどうやってやればいいのかわからない…」「性格検査の結果を用いて自己分析をしたい!」という方は、「SPIマスター」を申し込むことをおすすめします!
SPIマスターの特徴は以下の通りです。
- SPIと同様の検査だからそのまま本番に活かせる!
- 性格検査の結果から自分の性格が客観的に把握できる!
- 人事目線での結果に対するフィードバックを受けられる!
結果を確認できるからこそ、自己分析を効率的に進めることができます。
「SPIマスター」の申し込みはこちらから!
企業研究を行う
面接で落ちる人の多くは、企業研究を十分に行っていないことが原因の一つです。企業研究を怠ると、面接で曖昧な回答しかできず、熱意が伝わりにくくなってしまいます。
例えば、「御社の成長性に魅力を感じました」といった抽象的な回答では、他の企業でも通用してしまい、説得力に欠けます。企業の理念や事業内容、競合との違いを理解した上で、自分が企業に感じた魅力を具体的に伝えることが重要です。
また、企業研究を深めることで、逆質問の際に的確な質問ができ、意欲の高さをアピールできます。面接に合格するためには企業研究を行い、説得力のある回答を準備することが効果的です。
面接の一連の流れをイメージする
面接に落ちる人は、面接の流れをイメージするようにしましょう。
「入室 → 自己紹介 → 質疑応答 → 逆質問 → 退室」
面接には、上記のような一連の流れがあります。この流れを把握していないと、慌てたり、適切な回答ができなくなったりする可能性があります。
面接の一連の流れをイメージすることで、入室時の挨拶のし忘れを防いだり、逆質問にしっかりと備えることができます。落ち着いて本番に臨むためにも、面接の流れをイメージするようにしましょう。
まとめ
- 面接で落ちる人には共通の特徴がある
- 企業は面接において、「コミュニケーション能力」「企業との相性」「成長意欲」を重視している
- 「身だしなみを整える」「自己分析を行う」「面接の一連の流れをイメージする」「企業研究を行う」を意識して行う
本記事では、面接に落ちる人の特徴やその対処法について紹介しました。面接で合格をもらえないことで自信を失わず、失敗を次に繋げる糧として次の面接に活かしましょう。
対策を十分に行えば、最後には必ず内定をもらうことができるはずです。
人気記事