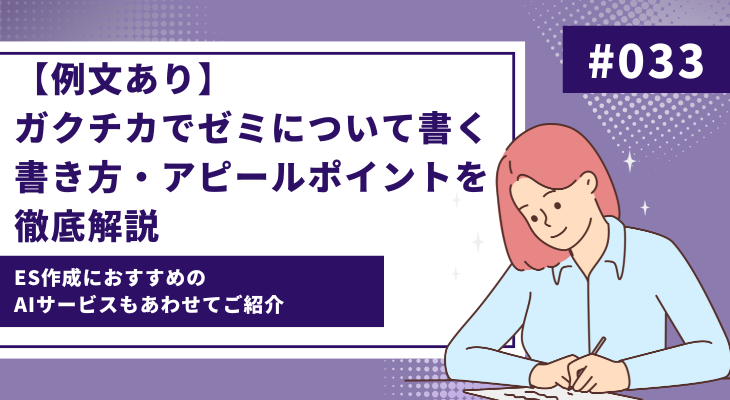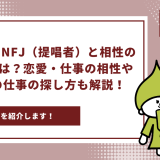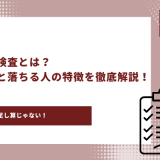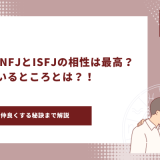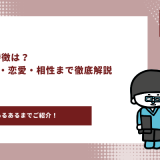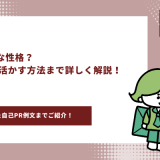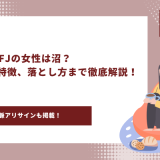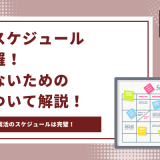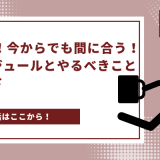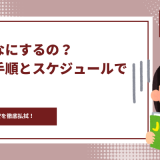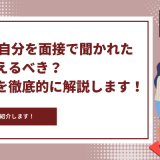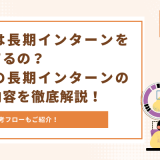就活を始める皆さん!ガクチカでゼミについて書きたいと考えている学生さんはいませんか。ですが、どうやってガクチカでゼミについて書けばいいか分からないですよね。
そんな学生さんに向けて、今回はゼミでのガクチカのおすすめの書き方やアピールポイントを解説していきます!
最後には、ガクチカ作成をサポートしてくれる便利なサービスも紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
この記事でわかること
- ガクチカでゼミでの経験について書きたいと考えている人
- ガクチカでゼミでの経験を伝えて、他の学生と差別化を図りたいと考えている人
- ガクチカでゼミの経験を自分で上手く書けないと悩んでいる人
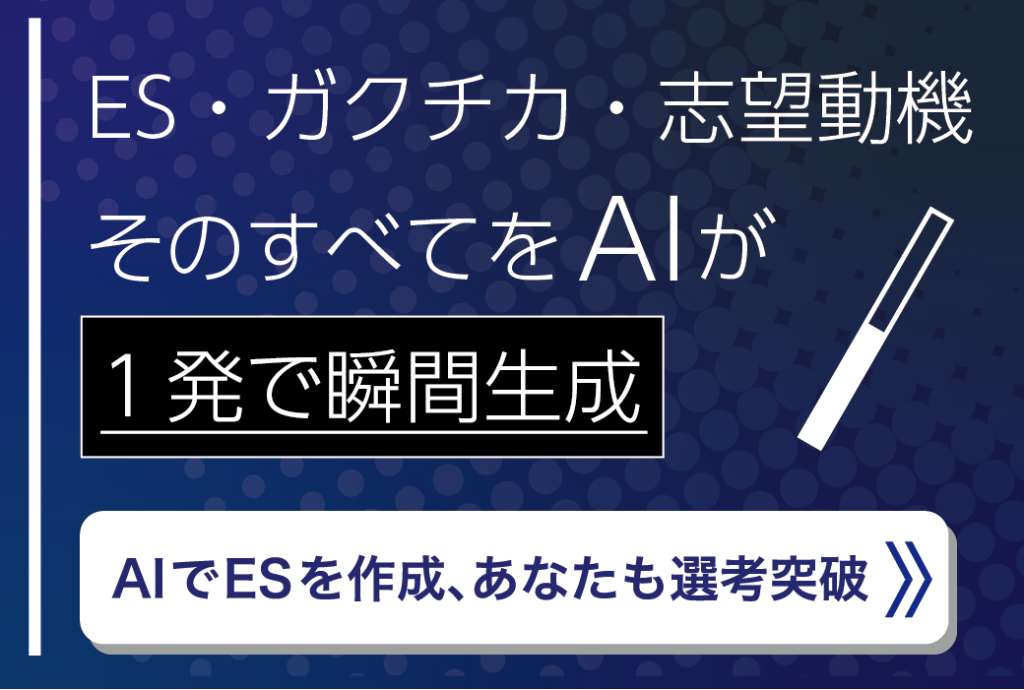
ESやガクチカで困っているならES生成AIであるSmartESがおすすめです!
ES生成AIとは就活や長期インターンのサポートに特化した生成AIのことです。
ES生成AIであるSmartESに質問とそれに対する簡単な回答を打ち込むと、自動でES、ガクチカ、志望動機を生成してくれます!
SmartESの強みは以下の4つです!
- 数々の選考を勝ち抜いてきた10万本以上の良質なESをもとに生成しているため、就活に最適化されたESを出力できる!
- 入力するべきことがフォーマット化されていて簡単なので、複雑な指示は必要ない!
- 企業のURLを入力するだけで、その企業に合った志望動機を出力することが可能!
- 自分一人ではやりづらい添削もAIがやってくれる!
「ESやガクチカでどんな文章を作ればいいかわからない……」「作れたけどちゃんと良いものになってるか不安……」という人はES生成AIを使ってみてはいかがでしょうか?
SmartESを利用するにはこちらをクリック
ガクチカってどんなのを書けばいいの?

ガクチカとは「学生時代に力を入れたこと」の略で、就活で必ず聞かれる質問の1つです。
ガクチカでは具体的なエピソードを通して、どのような経験をし何を得たのかといったことをアピールします。
具体的には、ゼミやサークルなどの学校生活、アルバイトやボランティアの経験などから得た学びや困難を乗り越えた方法などを書きます。
ガクチカでゼミについて書いてもいいの?
「ガクチカをゼミの内容で書くのはありふれているのでは?」「ガクチカとして差別化できないかな。」と思う方もいると思います。
結論から言うと、ガクチカでゼミについて書いても問題ありません!
ですが、ゼミであればなんでも良いというわけではありません。ビジネスで活かせるような経験であることを伝えなくてはいけません。
ガクチカでゼミについて書く時にはこれから解説するポイントをしっかりと押さえて、最強のガクチカを書きあげましょう!
【おすすめ5選】ゼミのガクチカでのアピールポイント

「ガクチカをゼミの経験をもとに書きたいけど、どう書けばいいか分からない」「何をアピールしたらいいか分からない」という学生さんはいませんか。
具体的にどのような能力をアピール出来るのか解説していきます!
アピールできる能力は主に4つあるので、自分に合った能力を見つけて参考にしてみてください。後半でこのアピールポイント別に例文を紹介しているので、そちらも参考にしてください。
コミュニケーション能力
ガクチカをゼミで書く時にアピールできる能力1つ目は、コミュニケーション能力です。
コミュニケーション能力はどの会社でも必要とされる能力の1つであることに加え、営業など特定の職業では非常に強みになります。
グループディスカッションでの活発な意見交換や合意形成、研究発表における分かりやすい説明や質疑応答、共同研究を進める上での教授や他のメンバーとの円滑な連携や情報共有などが挙げられるでしょう。
ゼミ活動の中で、他者とどのように関わり、意思疎通を図り、協力して目標を達成したかという具体的なエピソードを交えて説明しましょう。例えば、意見が対立した際にどのように調整役を果たしたか、あるいはチームの士気を高めるためにどのような働きかけをしたかなど、主体的な行動を示すことが重要です 。
チームワーク
ガクチカをゼミで書く時にアピールできる能力2つ目は、チームワークです。
ゼミという組織ではチームワークが必要不可欠です。そして、会社もゼミと同様に組織であるため、プロジェクトなどチームワークが必要不可欠となる場面が多くあります。
ガクチカでチームワークをアピールすることで、会社といった組織で活躍できる人材であることをアピール出来ます。
グループ研究で役割分担し協力して課題に取り組む、メンバーの意見を尊重し建設的な議論を行う、チーム内で生じた意見の対立を調整するなど、チームの中で自身がどのような役割を担い、どのように貢献したのか、具体的なエピソードを交えて説明しましょう。
課題解決力
ガクチカをゼミで書く時にアピールできる能力3つ目は、課題解決力です。
ゼミではさまざまな課題が起こることもあるでしょう。課題をどのように解決したか過程を説明して、課題解決力をアピールしましょう。
先行研究の課題点を指摘し新たな研究課題を設定する、実験がうまくいかない原因を特定し改善策を講じる、グループ発表の準備で意見がまとまらない際に打開策を提案するなど、どのような課題に直面し、その本質をどう捉え、どのような思考プロセスを経て解決に至ったのか、具体的な行動とそこから得た教訓をアピールしましょう。
統率力
ガクチカをゼミで書く時にアピールできる能力4つ目は、統率力です。
これは特に、ゼミ長などマネジメントする立場であった学生さんが強くアピール出来るでしょう。ゼミでは、グループでプロジェクトを進めたり、ディスカッションをする機会なども多いですよね。
ゼミ長としてゼミ運営を円滑に進める、グループ研究でリーダーシップを発揮しプロジェクトを推進する、議論が停滞した際に新たな視点を提供し活性化させるなどリーダーシップを発揮した場面はたくさんあるでしょう。 具体的な目標設定、チームをまとめるために行った工夫、困難を乗り越えた経験などを通して、どのようにリーダーシップを発揮したかを話しましょう。
ゼミのガクチカを書くメリット

ガクチカをゼミで書くことでアピール出来る能力がたくさんあることが分かったと思います。
ここからは、具体的にガクチカをゼミで書くことのメリットは何があるのか解説していきます。
ガクチカをゼミで書くメリットは主に3つあります。
イメージしやすい
ガクチカをゼミで書くメリット1つ目は、イメージしやすいことです。
面接を行う人事や経営陣も同じく大学でゼミを経験している人が多いでしょう。誰もが想像しやすい経験をもとにガクチカとして話すことで、あなたの強みなどを明確に伝えることができるでしょう。
組織における役割を伝えやすい
ガクチカをゼミで書くメリット2つ目は、組織における役割を伝えやすいことです。
ゼミは個人だけでなく、複数人で組織となって行うことが多いですよね。
企業も1つの組織です。組織において、リーダーが得意なのか、縁の下の力持ちタイプなのかなどと入社後をイメージしやすくなります。
被りにくい
ガクチカをゼミで書くメリット3つ目は、被りにくいことです。
「ゼミってみんなが入るし、ガクチカとしては被りそう」と思うかもしれません。確かに、「ゼミ」という点では被ることも多いかもしれませんが、ゼミでの研究テーマなど詳細まで被ることはあまりないですよね。
そのため、自分だけのエピソードを実は話しやすいのです。
【テンプレート付き】ゼミのガクチカの書き方
ここではES等で実際にゼミのガクチカを書くときの書き方について解説していきます。
ガクチカの書き方のテンプレート
まず、ガクチカを書く際の基本的な型について簡単に紹介します。
- ➀私が力を入れたことは〇〇です。
- ②〇〇では△△をしていました。
- ③初めは〇〇が課題で上手くいきませんでした。
- ④しかし〇〇をしたことでその課題を乗り越えることができました。
- ⑤この経験を経て私は〇〇を学びました。
- ⑥貴社ではここでの学びを活かして〇〇ができるようになりたいです。
➀結論を書く
最初は絶対に結論から書くようにしましょう。
結論を頭に持ってくることは、プレゼンや面接の際にも重要なポイントとなるので、しっかりおさえておくようにしましょう。
②取り組んだことの説明を簡単に書く
続いて、その取り組みについての簡単な説明と具体的に何をやっていたかを記載します。
説明がないと、自分の伝えたいことがうまく面接官に伝わらない事があります。エピソードが複雑な場合は、特に丁寧に書きましょう。
③課題だったことを書く
次にその取り組みの中でぶつかった壁や辛かったことを書きます。曖昧だと、次の文章に繋げにくいため、具体的に書きましょう。
④改善策と結果を書く
課題を書いたら、次はそれをどうやって乗り越えたのか書きます。課題を乗り越えることができた理由や方法などを書きましょう。
また、課題を乗り越えたあと、どうなったかについて数字も一緒に書くようにすると説得力が増すのでおすすめです。
⑤そこから何を学んだのかを書く
次にその経験から何を学んだのかについて書きます。この学びは入社後どう活きるかに繋げます。
⑥学びが入社後どう活きるかを書く
最後に経験から得た学びがその企業でどう活きるかについて書きましょう。
ガクチカを書いて終わりではなく、ガクチカをどう今後に活かしていくのかアピールしましょう。
ガクチカをゼミで書く時の注意点
ガクチカをゼミで書く時には、今から解説する注意点をしっかりと押さえて書きましょう。
過程を意識する
ガクチカをゼミで書く時の注意点1つ目は、過程を意識することです。
ガクチカを書く時には、成果が見えやすい結果ばかりを書いて、過程を書くことをおろそかにしてしまいがちです。結果をアピールすることは大切ですが、過程も結果と同様にあるいは結果以上に重要な部分です。
どのようにその結果に至ったのか、どのように努力したのかなどといった過程を必ず意識して伝えるようにしましょう。
専門用語の扱い方
ガクチカをゼミで書く時の注意点2つ目は、専門用語の扱い方です。
ガクチカをゼミで書く時に専門用語を当たり前のように書いてしまっていませんか?
自分にとっては当たり前の知識であっても、他の人にとっては当たり前の知識ではないかもしれません。誰にでもエピソードが伝わるように専門用語はなるべく使わないようにしましょう。
もし、どうしても使いたいという場合は必ず説明するようにしてください。
【アピールポイント別】ガクチカ例文10選
ここからはガクチカでゼミについて書く時に、どのように書けばいいのかこれまで解説したポイントを押さえた例文を200字程度のものと500字程度のもので字数別にご紹介します。
先ほど解説したアピールポイント別に紹介します。実際の内定者のものを参考にしておりますので、ぜひ自分のガクチカを書く際に活用してくださいね。
コミュニケーション能力
ガクチカをゼミで書く時に、コミュニケーション能力をアピールポイントにする際の例文はこちらです。
コミュニケーション能力を身につけたきっかけやその結果どういった影響が周囲に出たのかまでアピールしましょう。
コミュニケーション能力①
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミでの研究を通じてコミュニケーション能力を鍛えたことです。
「地域活性化のための若者支援」をテーマに研究を進める中で、幅広く意見交換を行うことが重要だと感じました。そこで、私はゼミメンバーだけでなく、自治体職員や地域の若者団体、住民の方々にも積極的に話を聞きに行き、自分たちの視点だけでなく、彼らの視点やニーズを研究に反映しました。
結果として、現場のリアルな声を踏まえた説得力のある研究内容を発表することができました。
コミュニケーション能力②
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミでのグループ研究です。
私のゼミでは、チームごとに異なるテーマについて研究を行い、学期末に発表する課題がありました。私はチームリーダーとして、メンバーの意見を引き出しながら、全員が納得できる研究テーマを決めようと努めました。
テーマが決まった後でも意見が対立することは多く、最初は議論がまとまらないことが課題でした。そこで私は、まず全員の意見を一度書き出し、それぞれの意見の背景や根拠をシートに管理し、可視化するよう心がけました。また、メンバーが積極的に発言しやすい雰囲気を作るため、リーダーとして中立的な立場を意識しました。
その結果、メンバー全員が納得できる研究テーマを決め、研究の過程でも互いに意見を出し合う風通しの良い環境を作ることができました。最終的に、私たちのグループの研究はゼミ内で最優秀賞を受賞しました。この経験を通じて、相手の意見を尊重しながらもスムーズに議論を進めるコミュニケーション能力を磨くことができました。
プレゼンテーション力
ガクチカをゼミで書く時に、プレゼンテーション力をアピールポイントにする際の例文はこちらです。
プレゼンテーション力が入社後の業務でどう活きるかまで言及しましょう!
プレゼンテーション力①
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミでのプレゼンテーション力の向上です。
ゼミ内で行われた「地域交通の改善策」という研究発表では、専門用語が多く難解になりがちな内容を、分かりやすく伝えるための工夫が求められました。
私は、図表やイラストを活用して視覚的に情報を整理し、話し方もポイントを絞り、聴衆が理解しやすい構成を意識しました。その結果、ゼミ内での評価が高まり、学内の発表会にも推薦され、審査員から「視覚効果をうまく活用し、内容が非常理解しやすいものであった。」との好評をいただきました。
プレゼンテーション力②
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミでのプレゼンテーションです。
ゼミでは学期末に各チームで行った研究成果を発表する課題があり、私たちのチームは「現代社会における情報拡散の影響」をテーマに研究を進めました。しかし、テーマが新しく情報の少ないものであることやその複雑さから、内容をわかりやすく伝えることが大きな課題でした。
私はチームの発表を担当し、内容構成とスライド作成に特に注力しました。研究の背景や目的、結果を簡潔に整理し、それぞれの要点が一目でわかるように心理学などを利用して、視覚的な資料を多く取り入れました。また、聴衆の関心を引き付けるために、テーマを発表する前に実例を取り上げ、それを研究内容に結び付ける形でストーリー性を持たせたプレゼンテーションを行いました。
その結果、私たちの発表は「最優秀プレゼンテーション賞」を受賞し、内容だけでなく、伝え方にも高い評価をいただきました。この経験を通じて、複雑な内容を整理し、相手にわかりやすく伝える力を磨くことができました。このプレゼンテーション能力は、今後どのような場面でも活かせると自信を持っています。
チームワーク
ガクチカをゼミで書く時に、チームワークをアピールポイントにする際の例文はこちらです。
ガクチカでチームワークをアピールする時にはただ仲良く行なったなどというエピソードではなく、主体的に行動したエピソードを書きましょう。
チームワーク①
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミでの研究を通じたチームワークです。
「観光地の環境保全策」をテーマにした研究では、メンバー間で意見が分かれる場面がありました。その際、私は一方的に意見を押し付けるのではなく、全員の意見を公平に聞き、それぞれのアイデアの長所を活かす方法を模索しました。
役割分担を明確にし、各自の意見や得意な部分を活かせる形でプロジェクトを進行しました。その結果、ゼミ内での最優秀プロジェクトに選ばれることができました。
チームワーク②
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミでのチーム研究です。
ゼミでは4人1組で議題を設定し、その成果をプレゼンテーションする研究課題がありました。私たちのチームは「SNSを活用した地域活性化」という議題を設定しましたが、各自の地域活性化の方向性が異なり、議論がなかなか進まないという課題がありました。
私は、全員が納得できる方向性を見つけるために、メンバー全員の意見を丁寧に聞き、それぞれの意見の良い点を組み合わせることを提案しました。また、役割分担においては、メンバーの得意分野を活かせるよう調整し、効率的に作業を進める工夫をしました。たとえば、分析が得意なメンバーにはデータの収集と解析を、表現力に優れたメンバーにはスライド作成を担当してもらいました。さらに、授業外でも週に1度オンラインでミーティングを行い、全員で進めるということにこだわりました。
その結果、メンバー全員が主体的に取り組み、研究内容を無事に発表まで仕上げることができました。ゼミ内では、「チーム全体の連携が非常に良かった」と高い評価をいただきました。この経験を通じて、チーム全体をまとめ、互いの強みを活かしながら成果を出すためのチームワークの大切さを学びました。この力は、今後どのような環境でも活かしていけると考えています。
課題解決力
ガクチカをゼミで書く時に、課題解決力をアピールポイントにする際の例文はこちらです。
課題を解決した過程やその評価についても言及しましょう。
課題解決力①
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミの研究を通じて課題解決力を鍛えたことです。
「地域高齢者の社会参加の促進策」をテーマに研究を進める中で、関連する先行研究が不足しており、研究の進行が滞る場面がありました。
私はまず問題の原因を分析し、必要な情報を補うため、フィールドワークやヒアリング調査を提案・実施しました。また、得られたデータを効率的に整理し、議論の基盤を作り直すことでプロジェクトの軌道修正を行いました。
これにより、研究は大きな成果をあげ、学内コンペで表彰される成果を収めることができました。
課題解決力②
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミでのプロジェクトを通して課題解決力を鍛えたことです。
ゼミの研究では、「若者の投票率向上に向けた取り組み」をテーマに進めていましたが、研究初期の段階で、必要なデータの収集が難航しました。具体的には、若者の投票行動に関する十分な統計資料が見つからず、研究の進行が大きく停滞してしまいました。
私は、まず情報が不足している原因を分析し、オンライン情報には限界があると考え、アプローチ方法を見直しました。具体的には、オンラインに加え、自治体やNPOに直接問い合わせるなどの手段を取りました。また、現役大学生を対象として自分自身でアンケート調査を実施し、独自のデータを収集することで情報の補完を試みました。
これらの取り組みによって、研究に必要な基礎データを確保し、当初予定していた分析を進めることが可能になりました。最終的には、研究成果がゼミ内で高く評価され、過去の参考例として紹介されるまでに至りました。この経験を通じて、問題が発生した際に原因を素早く分析し、行動を起こすことで課題を解決できる力を身につけることができました。
統率力
ガクチカをゼミで書く時に、統率力をアピールポイントにする際の例文はこちらです。
具体的な研究テーマや過程で起こった困難についても言及するのが大切です。
統率力①
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミのプロジェクトの成功です。
「商店街活性化の戦略」をテーマとした研究では、私はチームリーダーとしてプロジェクト全体を統括しました。メンバー間でスケジュール管理や役割分担に混乱が生じる中、私は進行状況を可視化するためにタスク管理ツールを導入し、定期的なミーティングを行うことで全員の意識を向上するとともにすり合わせを行いました。
その結果、全メンバーが役割を果たし、研究成果は発表会で高く評価され、地域住民の方々からも実現可能性について非常に期待する声をいただくことができました。
統率力②
私が学生時代に力を入れたことは、ゼミでのグループ研究をリーダーとして成功に導くことです。
ゼミでは「地域社会における高齢者の孤立を防ぐ取り組み」をテーマに研究を進めることになり、私はチームのリーダーを務めました。しかし、初期段階ではメンバーの間で意見がまとまらず、進捗が当初予定よりもかなり遅れてしまいました。
私はまず、全員が共通の目標を持つことが重要だと考え、初回のミーティングでプロジェクトのゴールを明確にし、各メンバーがテーマに対してどのような意見を持っているかを丁寧にヒアリングしました。その上で、役割分担を適切に行い、得意分野を活かせるタスクを割り振るよう努めました。また、研究が円滑に進むよう、進捗管理シートを作成し、定期的に状況を確認して必要に応じて計画を修正しました。
さらに、チームのモチベーションを維持するために、小さな成果や進捗があればその都度メンバーにフィードバックし、感謝の気持ちを伝えることを心がけました。その結果、全員が主体的に取り組むようになり、研究は予定通りに完成しました。最終的にはゼミ内で「最も協調性のあるチーム」として評価され、研究発表も成功を収めました。
この経験を通じて、メンバーをまとめ、全員が持てる力を発揮できる環境を作る統率力の大切さを学びました。この力は、今後の仕事でもリーダーシップを発揮する上で役立てられると考えています。
もう自分でガクチカを書かなくてもいい⁉
ここまで、ガクチカをゼミで書くことについて解説してきました。
ですが、なかなか自分でガクチカを書くとなると難しいですよね。
そんな学生さんに朗報です!もう自分でガクチカを書かなくてもいいんです。「どういうこと?」と困惑した方もいらっしゃるかもしれません。どういうことかというと、自分でガクチカを書く代わりにAIを使って書くことができるのです。
そこで、おすすめのAIサービスがSmartESです。
SmartESとはES作成に特化した生成AIサービスで、今までのAIサービスとは大きく異なる新しいサービスです。
このサービスでは、約10万件の優秀なESデータをもとに、自分の強みをアピールできるガクチカを書いてくれます。1から生成するだけでなく、自分で書いたガクチカの添削なども出来るのでぜひ利用してみてください。
SmartESを利用するにはこちらをクリック
まとめ
この記事を要約すると以下の通りになります。
- ガクチカをゼミで書くことはメリットがたくさん!
- ガクチカをゼミで書くと様々な能力がアピールできる
- ガクチカを書く時におすすめなサービスはSmartES
この記事では、「ガクチカをゼミで書きたい!」思っている学生さんに向けて、ガクチカをゼミで書くメリットや注意点と合わせておすすめのAIサービスなどを解説してきました。
「自分で上手くガクチカが書けているか不安…」「ガクチカで他の学生と差をつけたい!」という学生さんはぜひこの記事で紹介したSmartESを使ってみてください。
ガクチカはどの企業でも聞かれる非常に重要な質問です。自分らしい最強のガクチカを作り、内定へとつなげましょう!
この記事があなたの助けになれば幸いです。
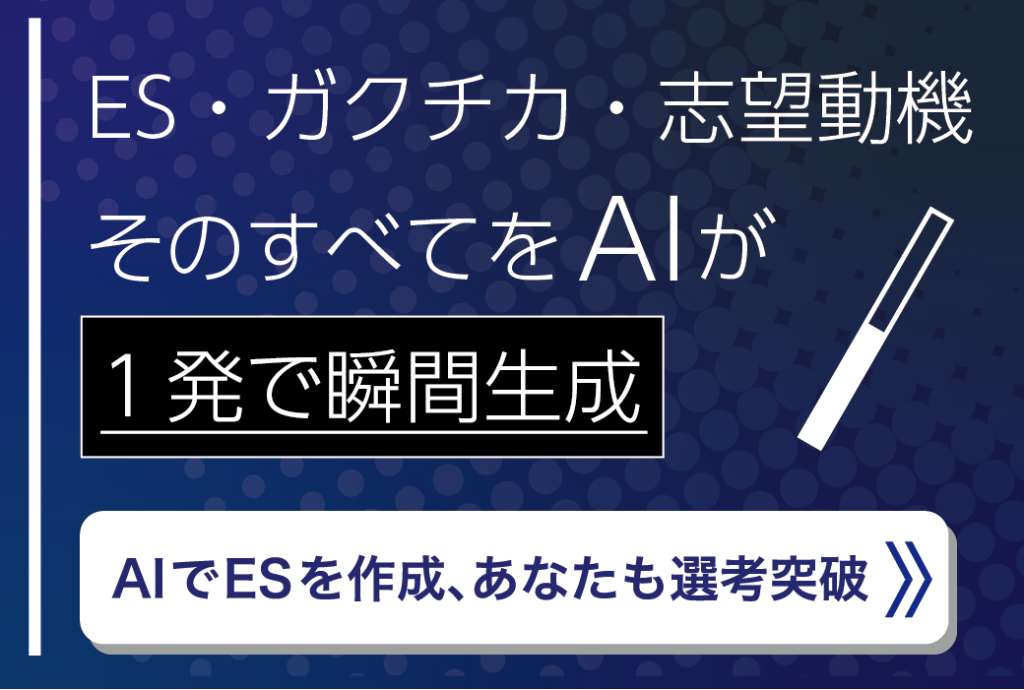
ESやガクチカで困っているならES生成AIであるSmartESがおすすめです!
ES生成AIとは就活や長期インターンのサポートに特化した生成AIのことです。
ES生成AIであるSmartESに質問とそれに対する簡単な回答を打ち込むと、自動でES、ガクチカ、志望動機を生成してくれます!
SmartESの強みは以下の4つです!
- 数々の選考を勝ち抜いてきた10万本以上の良質なESをもとに生成しているため、就活に最適化されたESを出力できる!
- 入力するべきことがフォーマット化されていて簡単なので、複雑な指示は必要ない!
- 企業のURLを入力するだけで、その企業に合った志望動機を出力することが可能!
- 自分一人ではやりづらい添削もAIがやってくれる!
「ESやガクチカでどんな文章を作ればいいかわからない……」「作れたけどちゃんと良いものになってるか不安……」という人はES生成AIを使ってみてはいかがでしょうか?
SmartESを利用するにはこちらをクリック
人気記事